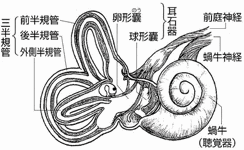 図1:耳の構造
図1:耳の構造 加速度による危険度の実証実験
141017 荒井勇樹
141498 戸口文雄
<序論>
「普段通学に交通機関を利用する中で、体感的に電車よりバスの方が危険に感じる。」という感覚を科学的に実証してみよう、というのが動機である。実験の目的はそれぞれの乗り物での観察の中で、1、危険と感じる加速度、2、実際のバスと電車の加速度を比較を行い「危険」を証明することである。
この実験に際し、事前に走行時の規則をバスにおいては関連法規を・電車においてはJR東日本の車両仕様を参照した。バスにおいては走行時の速度とは別に加速度を基準として交通法規に審査基準が記載されていた。自動車2種免許試験における減点基準として、0.4Gを超える加速度で急発進した時(特別減点項目)減点5点、また0.4Gの減速度で制動した時(特別減点項目「制動不円滑」)減点5点など大型自動車の発進・停止・右左折時などにおいてそれぞれ基準があった。これらは、走行時の乗客の安全を担保する交通機関として守られるべき基準である。また、電車においては今回測定に利用したJR東日本京浜東北線のE233系の車両仕様として、起動加速度:2.5 Km/h/s (0.7 m/s/s)、減速度:5.0 Km/h/s (1.4 m/s/s) と、その発停車時におおける基準が設定されていることが確認された。
一方で、危険を感じる側である人間の構造においても揺れに対する危険から経験的に自己防衛能が働くという可能性が考えられたため、人間の平衡機能に働く感覚と人間の体の重心について調査した。
人間の平衡機能は、平衡感覚・視覚・深部知覚の三つの感覚によって保たれている。
視覚は目から入ってくる情報であり、平衡感覚は内耳にある三半器官が3-D方向に異なる器官を持つことでそれぞれの方向に対する傾きを感知することができる。
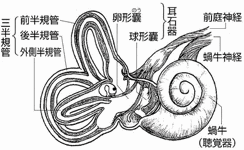 図1:耳の構造
図1:耳の構造
また、深部感覚は、位置覚、運動覚、抵抗覚、重量覚により、体の各部分の位置、運動の状態、体に加わる抵抗、重力を感知する感覚のことである。これらの感覚から得られる情報を脳内で統合することにより、人間は体の平衡を保とうとする。
また、人間の重心は、北海道工業大学の実験によると足から55%のところにあると測定された。この実験により少なくとも体の上半身に体の重心が位置していることが確認できた(下図2)
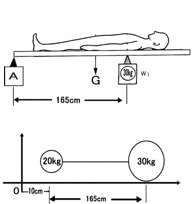
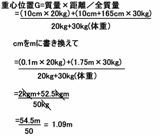
![]()
これらの情報をもとに、普段の経験から「比較的安定だ」と考えている電車と「危険である」と考えられているバスの走行時の加速度を実際に実験者の1人の通学路である、品川~東京間、三鷹~ICU間の測定結果を用いて比較した。
この実験を通してそれぞれの乗り物の危険性を加速度の点から明らかにすることで科学的に「危険」を証明することをこの実験の目的とした。
<方法>
今回の実験では、測定機器としてApple社のipod touchとソフトバンクモバイルから販売されているiphone4に内臓されている 3軸加速度センサーと、無料アプリケーション・ソフトSPARKvueを用いて加速度の測定を行った。
このアプリケーションでは、図3のように測定機器の長辺側をy軸(前後方向)、短辺側をx軸(左右方向)、画面から上方向にz軸の測定を行うことができる。
その加速度は内臓の計算システムによりG-Forceとして自動的に計算され、gまたはm/s/sとして時間軸の変化に伴って表示される。
測定は、小田急バス(三鷹~ICU間の往来、図4)、電車(JR東日本京浜東北線品川~東京間、図5)を利用し、それぞれに取り付けて発車と同時の測定を行った。
これらの順路の選定は今回の目的が普段利用する乗り物の危険性を再考するというものであるため、実験者の1人の通学路にあたる三鷹‐ICU間のバスと京浜東北線品川‐東京間を利用した。この品川東京間を測定した目的として、下図5、6に示してある場所において線路の転換が行われており、乗車時には大きな揺れを感じるためで、危険度の比較のためにこの地点を含む区間での測定を行うことになった。
実際には天候や混み具合、時間帯などによって異なるが、今回は複数回にわたるデータを総括的に捉えていくため、これらの要素は考えず測定を行った。
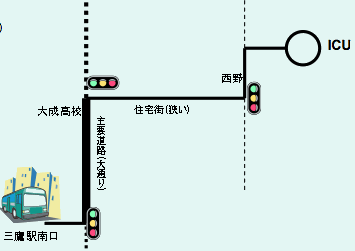
図4:三鷹~ICU間バスルート
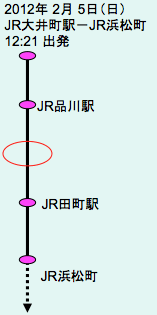
図5:JR京浜東北線品川東京間
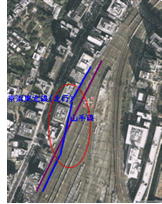
図6:転換点の航空写真(右)
<結果>
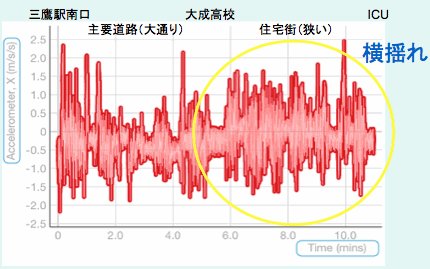
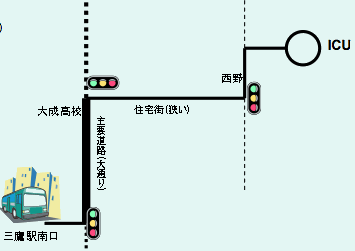
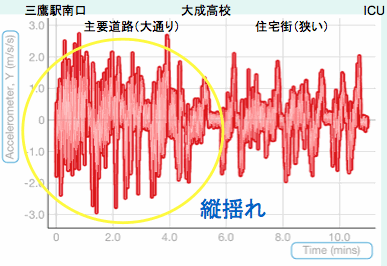
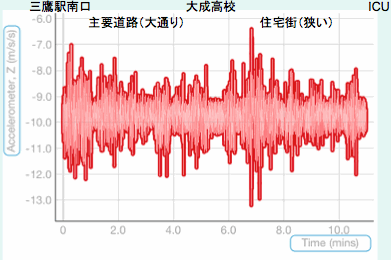
実験のすべての結果はこのレポートの最後に添付することにするが、データから読み取られた内容を描写するためにデータの一部をここでは利用することとする。関連法規に記載されていた安全性を保つための危険度と比較すると。今回の実験では、特記するような「危険」は測定されなかった。JRの車両仕様による加速度が1.4、測定値1.0また、交通法規による加速度3.9、測定最大値が3.0(それぞれ単位m/s/s)であった。しかし、多くの測定結果で、大通りと住宅街を走行する際には特徴がみられた。大通りを走行する際には縦揺れが大きく、住宅街を走行する際には横揺れが大きいことが観察できる。
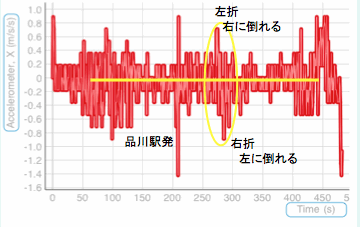
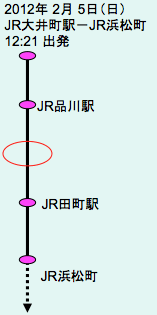
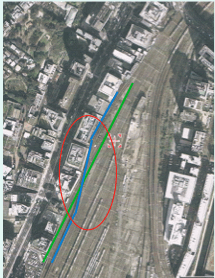 (緑線:山手線、青線:京浜東北線)
(緑線:山手線、青線:京浜東北線)
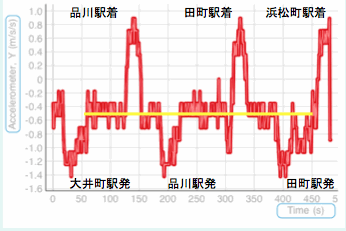
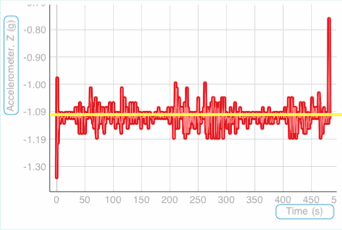
一方、京浜東北線での加速度の測定は上図のように顕著な加速度の変化が観察された。発着時の際にはほぼ一定の加速度が測定された。ただ、この測定でも危険を伴うとされるような値は得られなかった。今回注目していた線路が交差するポイントでは、その加速度は比較すると、駅での発車などと比べると大きな値を示すことはなかった。
<議論>
三鷹‐ICU間のバス走行時では、x、y、zそれぞれの軸方向に大きな特徴的な加速度の変化は観察されなかった。
z軸方向では、常に‐1G前後の加速度がみられた。これは、地球上の物質すべにかかる重力加速度(1G、9.8m/s/s)に相当するものであると想定でき、等加速度はその変動に影響を与えない範囲と考えられた。
また、x、y軸においてはいずれのデータにおいても加速度に一定の増減の値が観察されたが特記する変化の大きさではないと判断できる。
y軸のデータにおいて大通り(三鷹駅南口から大成高校)と小さな通り(大成高校から西野)の走行時において明らかな違いが現れた。大通りを走行時の変化が住宅街を走行時に比べ大きいことが確認できた。これは大通りでの走行が小さな通りでの走行に比べ速度が速く、アクセルやブレーキの踏みこみが比較的大きいことが要因ではないかと想定できる。
京浜東北線での加速度の測定では、電車の加速・減速に伴う顕著な加速度の変化が観察された。ただ、この測定では加速度が1.0m/s/sを超えることはなく、危険とされるような値は得られなかった。今回注目していた線路が交差するポイントでは、その加速度は比較すると、駅での発車などと比べると大きな値を示すことはなかった。よって、普段乗客が感じている大きな揺れが電車の加速度変化によるものではないという可能性がある。
一方で、揺れを感知する側の人間の身体の構造により揺れを感じやすくする働きがあるのではないかと想定することもできた。人間の平衡機能は平衡感覚・視覚・深部知覚から得られる情報を統合することによって保たれている。よって人は揺れを感じると経験に基づく自己防衛本能が働き平衡を保つのではないかと考えられる。しかし、その情報の一部が欠けることで平衡機能を正常に機能しなくなり、本来の揺れ以上に危険を感じ取ってしまうのではないかと想定できる。特にバスの場合、座席からは前方からの情報が限られるため、突発的なものとして揺れを感知することでその大きさが比較的小さくても危険に感じられるのであろうと想定できる。
また、体の重心の位置が足元から55%にあるため、重心が上半身に位置することになる。この重心の位置が上にあればそれに伴って揺れ(身体的領域)を強く感じやすくなると想定できる。
<結論>
今回の実験では日常生活で利用するバス・電車の危険性を測定した。
その危険性は、加速度の測定によってバス・電車の危険性が人為的(運転手)な領域では、概ね人間の安全を担保する範囲であることが実証できた。
しかし、加速度は車両仕様および審査基準等により安全を担保していることから加速度が安全性に与える影響は存在すると想定できる。
また、揺れが加速度によって大きく測定されない地点においても揺れが大きく感じられたことは、揺れによって危険を感知する人間の身体的機能が影響するのではないかという想定ができた。
今回の目的である危険度の測定をすることはできなかった。また電車とバスの加速度の比較では、測定値の最大が1.0と3.0(どちらも単位:m/s/s)であることからバスの方が潜在的に危険性が潜んでいると考えられる。
<参考文献>
電車のこころえ
http://www.geocities.jp/untiyan/buskokoroe.html
平衡感覚
http://ja.wikipedia.org/wiki/平衡感覚
電車図鑑
http://www.asahi-net.or.jp/~eg6f-tkhs/tetu/
北海道工業大学
http://www.hit.ac.jp/~gisisougu/COGkeisan.html
<補足>
参考データ(観測日時ごと)
グラフ(観測日時ごと)