���ۊ����w
GE�����w�̊�b�ƊT�O
�����G������
�a�c 161539
���{ 161434
�O�X 161258
�O�D 161246
����
group1���|�[�g
2013/3/1
Group1 �e�B�b�V�����̎d�g�� �ŏI���|�[�g
�A�E�g���C��
1.�T�v
2.��s�����A�w�i
3.�W����Ǝv����v�f�A����
4.����(1)
5.����(2)
6.����(3)
7.����(4)
8.�l�@
9.�܂Ƃ�
10.���_
1.�T�v
�e�B�b�V�����̎d�g�݂ɂ��āA
(1)�ꖇ���o�Ă��闝�R�A(2)���̈ꖇ���o�Ă��闝�R
�ɂ��čl�@����B
2.��s�����A�w�i
�Ȃ��e�B�b�V�����ꖇ���o�Ă���̂��A�܂��A�Ȃ����̈ꖇ�������Əo�Ă���̂��ׂ��B���̃e�[�}��I���R�͓��퐶���ŋC�ɂȂ�������ł���B�����̂��Ƃׂ邽�߂ɂ܂����������Ŏ��ۂɎ������Ă݂��B�����āA���̎������番���������ƂƂ��Ď��̂悤�Ȃ��̂���������B
���e�B�b�V���ɂ͗��\������
���o���̃r�j�[���͕Б��݂̂ł��A�Ȃ��Ă��o��
�����̌`��͍��{�I�ɂ͊W������
���e�B�b�V���̐܂��
���ꖇ���ł��݂��ɂ�����
�����o�������͂��܂�W�Ȃ�
�܂��A�e�B�b�V���ɂ͗��\�������ēd�Ȃ��ăe�B�b�V���ꖇ�ɂȂ��Ă��邱�ƁB���ƕ\�̑g�ݍ��킹��ς��Ă���Ă݂����A�ǂ̑g�ݍ��킹�ł���������o�Ă����B�e�B�b�V���̍\���͏�̎��̉��̕��������̎��̏�̕����ƂŌ��݂ɏd�Ȃ荇���Ă��邱�Ƃ��킩�����B�������A���S�ɏd�Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��āA��������ďd�Ȃ��Ă����B�r�j�[���̗L���┠�̌`��A���o�������ɂ͂��܂�W���Ȃ������B�`��Ɋւ��āA�����`�̔��ł������`�̔��ł������Əo���B�����ŁA�������̓e�B�b�V�����݂��ɂ������������炩�̗v���������ăe�B�b�V�����ꖇ���o�Ă���̂ł͂Ȃ��̂��ƍl���A���̗v���ɒ��ڂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B�@�����āA���Ɏ��ۂɃe�B�b�V����Ђɖ₢���킹�Ă݂��B�N���l�b�N�X�ƃl�s�A�ɖ₢���킹�Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�����B
�E�ŏ��l�܂��ďo�ɂ������R
���e�B�b�V����������ɍ����P~�Q�����̋�Ԃ��A�A���ߒ��Ŗc�����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����߁i�N���l�b�N�X�j
�E�Ȃ����\�ꖇ���d�Ȃ荇���Ă���̂�
�����G��A���x�i�N���l�b�N�X�j
���i�P�j�Q���d�˂��������炩���Ȃ�
���i�Q�j���̊Ԃɂł����C�w�Ő������z���i�l�s�A�j
�E�������S�ɑg�ݍ��킳���Ă���킯�łȂ��A����Ă��闝�R
���@�B�̓s���ジ���i�l�s�A�j
�����܂����ɓ���悤�ɒ������Ă��邽�߁i�N���l�b�N�X�j
���̖₢���킹�ł́A�e�B�b�V�����m�������������v���ɂ͌��y����Ȃ������B���\���ꖇ���d�Ȃ荇���Ă��闝�R�͒P�ɔ��G���ǂ����āA���x�������邽�߂ł�������A�����z�������������邽�߂ł������B�܂��A�e�B�b�V��������ďd�Ȃ��Ă���̂͋@�B�̓s����A�܂����ɓ���₷������Ƃ������P���ȗ��R�ł������B�e�B�b�V����Ђւ̖₢���킹�ł͎������̒��ׂ����v�����𖾂ł��Ȃ������̂Ŏ������͊W����Ǝv����v�f�ɂ��čl���Ă݂邱�Ƃɂ����B
3.�W����Ǝv����v�f�A����
��s���������Ƃɍl����ƁA�W����ł��낤�v�f�͎��̂��̂ł���B
�E�e�B�b�V���̍\��
�E�e�B�b�V������o���܂ł̋���
�E�e�B�b�V�����o���X�s�[�h
�E�e�B�b�V���̎����o��Ƃ���ɂ���r�j�[��
�E���C�A�Ód�C
��s�����ŁA�e�B�b�V�����o��������r�j�[���̗L���ɂ��Ă��܂�W���Ȃ��Əq�ׂ����A��������̎�ނ̎����͍s��Ȃ������߂ɊW����ł��낤�v�f�ɂ�����x�܂߂čl�����B�����������ڂ����e�B�b�V���������������v���ɂ́A���C�ƐÓd�C�̓�̗v���������čl���Ă݂邱�Ƃɂ���B
�@�e�B�b�V���͐�قǂ��q�ׂ����A�݂��Ⴂ�ɏd�Ȃ荇���Ă���B���̂悤�ȍ\���Ȃ̂ŁA��{�I�ɂ͎��̎����O�̎��ɂЂ��������ďo�Ă���B�ł́A�Ȃ������m�������t���ďo�Ă���̂��Ƃ������Ƃ��l�������ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��A���C�ƐÓd�C�ł���B�Ód�C�Ƃ́A�Q��ނ̈Ⴄ�������݂��ɂ����荇�킹�����ɐ��ƕ��̓d�ׂ������āA���̓d�ׂ̈ړ��ɂ���Ĕ���������̂ł���B�ł��A���������m�Ȃ�d�ׂ̕肪���܂�Ȃ����߂ɐÓd�C�͔������Ȃ��B�����ŁA�Ód�C�͊W�Ȃ��B���ɖ��C�ɂ��čl���Ă݂��B���C�ɂ͐Î~���C�͂Ɠ����C�͂̓��ނ���B�Î~���C�͂Ƃ́A�Î~���Ă��镨�̂������Ƃ��鎞�ɓ������C�͂ł���B�����C�͂Ƃ́A���̂��^�����Ă���Ƃ��ɕ��̂̉^����W��������ɓ������C�͂ł���B�e�B�b�V���͉^�����Ă��Ȃ��̂ŁA�Î~���C�͂��傫���e�����Ă���ƍl������B�e�B�b�V���������o�����߂ɂ́A�Î~���C�͂���͂��K�v�ł���B�e�B�b�V������������o���Ƃ��ɂ́A����n�_�ŐÎ~���C�͂���͂�������ꂽ���ɁA�e�B�b�V���͔������ƍl������B����āA�e�B�b�V���ɂ͐Î~���C�͂��������Ă���Ɖ��肷��B
������̎����ł́A�e�B�b�V���ɂ͐Î~���C�͂��������Ă���Ɖ��肵�āA�e�B�b�V������o���܂ł̋����A�e�B�b�V�����o���X�s�[�h�A�����ăe�B�b�V�����̃r�j�[���ȂǁA���������낢��ς��Ȃ������Ă����B
4.����(1)
�ړI�F�@�X�s�[�h�ƐÎ~���C�͂̊W
�����F
(1)�e�B�b�V�������O�i�ɏd�˂�
(2)�r�j�[������
(3)���������i�e�B�b�V���O�i���ɂ��j
���e�F
�X�s�[�h�@�����E�x�������Ŏ����B
�������ʁF
�����X�s�[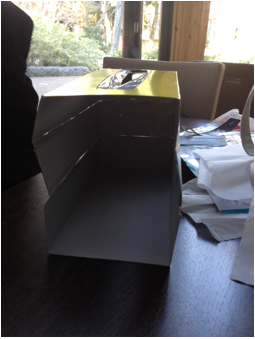 �h>>�o��
�h>>�o��
�x���X�s�[�h>>�o�Ȃ�
5.����(2)
�ړI�F�e�B�b�V���̏�ɂ��Ă���r�j�[���́A�ǂ��������������ʂ����Ă���̂��ׂ�B
���@�F�e�B�b�V�����i�ꔠ�j�̔����̗ʈȉ��E�ȏ�̗ʂ̃e�B�b�V���̎� / �r�j�[���Ȃ��E����
���ʁF
(1)�����̗ʈȏ�̏ꍇ�E�E�E�r�j�[���̗L���Ɋւ�炸�A�e�B�b�V���̓X���[�Y�ɏo��B
(2)�����̗ʈȉ��̏ꍇ�E�E�E�r�j�[��������Əo�邪�A�Ȃ��Əo�Ă��͂��ꗎ���Ă��܂��B
�@�@�@
�U�D����(3)
�ړI�F�r�j�[���̖����c�����Q���瓱�����u�r�j�[���̓e�B�b�V�����x���������S���Ă���v�̂ł͂Ȃ����Ƃ��������̌���
�����F(1)�O�i�ɏd�˂��e�B�b�V�����@���o���܂ł̋������������邱�ƂŁA���ʂ����N���ɂ���
�@�@�@�@(2)�����X�s�[�h�E�x���X�s�[�h
�@�@�@�@(3)���������i�O�i�e�B�b�V�����ɂ��j
���e�F�r�j�[���Ȃ�
���������F�����X�s�[�h�E�x���X�s�[�h�ǂ���̏ꍇ���e�B�b�V���͏o���܂œ͂����A�o���ɓ͂����ꍇ�ł��e�B�b�V���̈ꕔ���o��ɂƂǂ܂����B
|
�r�j�[���Ȃ� |
���� |
|
���� |
�~ |
|
�x�� |
�~ |
�V.����(4)
�ړI�F���̏o�Əo���܂ł̋����̊W�𖾂炩�ɂ���
�����F(1)�O�i�e�B�b�V����
�@�@�@�@(2)�����X�s�[�h�E�x���X�s�[�h
�@�@�@�@(3)�r�j�[���͕t�������
���e�F�@�߂������E��������
���������F
|
�r�j�[������ |
�߂� |
���� |
|
���� |
�� |
�� |
|
�x�� |
�� |
�~ |
8.�l�@
(1)����
�����Q�A�S���痧�ł���B
�����Q�ł́A
(1)��i�̒Z��������
(2)�r�j�[�����Ȃ���Ԃł�
(3)�����E�x�������̃X�s�[�h��
�e�B�b�V���͏o���B
�����R�ł́A
(1)�O�i�̉���������
(2)�r�j�[�����Ȃ���Ԃ�
(3)�����E�x�������̃X�s�[�h��
�e�B�b�V���͏o�Ȃ������B
�����ȊO�͎����Q�A�S�Ƃ��ɓ��������ł���̂ŁA�������e�B�b�V���̏o��A�o�Ȃ��ɐ[���W���Ă��邱�Ƃ��킩��B
(2)�r�j�[���F
����3,4�̉��������E�����X�s�[�h.�E�x���X�s�[�h�ł̎������ʂ��r����B
����3�̃r�j�[���Ȃ��̏ꍇ�ł́A�����X�s�[�h�E�x���X�s�[�h���Ƀe�B�b�V�����o�邱�Ƃ͂Ȃ��������A�����C�̃r�j�[������̏ꍇ�ł́A�����X�s�[�h�̎��ɂ̓e�B�b�V�����o�Ēx���X�s�[�h�̎��ɂ̓e�B�b�V�����o�Ȃ������B
����3,4�̏����̈Ⴂ�̓r�j�[���̗L���ł��邱�Ƃ���A�r�j�[�����e�B�b�V���̏o�ɉe����^���Ă���ƍl������B
(3)����
�����P���A
(1)�O�i�̉���������
(2)�r�j�[���������Ԃ�
(3)�����A�x�������̃X�s�[�h��
�e�B�b�V�����o���ƁA
�������o�₷��
�x�����o�ɂ���
���Ƃ���A�e�B�b�V�����o���ۂɂ́A��r�I�������x�ň����������ق��������o���₷�����Ƃ��킩��B
�܂��A���̌��ʂ���l�@�ł��邱�Ƃ��ȉ��̂悤�ɋ�������B
�X�s�[�h����: ��������́���C
�܂�A��C�̏d���ň�������ꂽ�e�B�b�V����
������܂łɑf������������Ƃ������ƁB
�X�s�[�h�x��: ��������́���C
�܂�A�x����������Ƌ�C�̏d���Ƀe�B�b�V�����ς����Ȃ��Ȃ�A
�͂��ꗎ���Ă��܂��Ƃ������ƁB
�� �Î~���C�͂������C�͂ɕς��O��
�@���̃e�B�b�V�����o���܂ŗU�����邱��
�@���o�邽�߂ɕK�v�ɂȂ�B
9�D�܂Ƃ�
�@���̏o���ƃe�B�b�V���̋������߂��Ƃ��F�@
���r�j�[���͖����Ă��o��B�Ȃ��Ȃ�A�e�B�b�V�����͂����O�A�������͂͂����r���̏�ԂŎ��̃e�B�b�V�������̒��ɖ߂�Ȃ��قǏ\���Ȗʐς��o������o�邩��ł���B�܂�A�Î~���C�͂������C�͂ɕς��O�Ɏ��̃e�B�b�V�����o���̊O�֗��܂�̂ɏ\���Ȗʐϕ��U���ł��邽�߁A�e�B�b�V���̓r�j�[���̗͂Ȃ��ŏo���̊O�ɏo�ė��܂邱�Ƃ��o����B���̂��Ƃ��番����̂́A�e�B�b�V�����͂����̂Ƀr�j�[���̗͂͊W���Ȃ����Ƃł���B
�����o���X�s�[�h�͊W�Ȃ��e�B�b�V���͏o��B�������o���ꍇ�́A��̃e�B�b�V���ɂ���������Ԃ������́A���͂�����̃e�B�b�V�����o������o�āA��Ɋ��S�ɂ͂����B�x�����o���ꍇ���A���������܂܁A���邢�͂͂���o������o�Ă��邪�A�o���Ƃ̋������߂����ߎ��̃e�B�b�V���͔��̊O�ɂƂǂ܂�̂ɏ\���Ȗʐς��o���̊O�ɏo��B
���̏o���ƃe�B�b�V���̋����������Ƃ��F
���r�j�[�����Ȃ��Əo�ɂ����B�Ȃ��Ȃ�A���̏o���ƃe�B�b�V���̋������������߁A���̃e�B�b�V�������S�ɂ͂����O�ɔ��̊O�ɗ��܂�̂ɏ\���Ȗʐϕ��U�����邱�Ƃ��������ł���B�܂��A�r�j�[��������Əo�₷�����Ƃ���A�r�j�[���͏o������o�Ă���e�B�b�V�����Ƃ炦�Ďx���A���ɖ߂�Ȃ��悤�ɂ��铭��������ƕ�����B
�����o���X�s�[�h���W����B�������x�Ŏ��o���ƁA�e�B�b�V���ǂ��������S�ɂ͂����O�ɏo���̊O�Ɏ��̃e�B�b�V����U�����邱�Ƃ��o���邽�ߐ�������B�x�����x�Ŏ��o���ƁA�e�B�b�V���ǂ��������S�ɂ͂��ꂽ�Ƃ����̃e�B�b�V�����o���̊O�ɏo�Ă��Ȃ����A�܂��͏����o�����r�j�[���Ŏx���邱�Ƃ̂ł���ʐϕ��o�Ȃ��������߂Ɏ��̃e�B�b�V���͔��̒��ɗ������Ď��s����B
�s���Ăȓ_�F�@�e�B�b�V���ǂ��������������Ƃ͐Î~���C�͂Ő����ł��邪�A�͂����v�������炩�ł͂Ȃ��B�����������e�B�b�V���̊p�x�A��C�̏d���A�܂����������Ă��Ȃ��c��̃e�B�b�V���̏d���Ȃnj�����K�v���������B�������琄������ɁA�O�q�̗v���͑S�Ċ֗^���Ă���Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�A�e�B�b�V������蔠�Ɛ����ɂȂ�p�x�ň�������قǂ͂���₷���Ƃ������A�܂���C�̏d���Ǝc��̃e�B�b�V���̏d���͖��炩�Ɉ��������Ă���̃e�B�b�V���ɂ������Ă���Ǝv���邩��ł���B
10�D���_
���e�B�b�V�����ꖇ���o��d�g�݂́A�ȉ��̒ʂ�ł���B�e�B�b�V���͈ꖇ�ꖇ�����ɐ܂��A���̐܂�ꂽ���������ꂼ�ꓯ�l�ɐ܂�ꂽ��̃e�B�b�V���Ɖ��̃e�B�b�V���̓����Ɛڂ���\���ɂȂ��Ĕ��ɓ����Ă���B�e�B�b�V���ǂ����͂�������Ƃ��݂��ɂ������悤�ɐ܂荇�킳��Ă���B���������āA��̃e�B�b�V������������ƐÎ~���C�͂������Ď��̃e�B�b�V������̃e�B�b�V���ɂ������ďo���ɓ��B���A��C�̏d�����c��̃e�B�b�V���̏d�������炩�̗v���ŐÎ~���C�͂������C�͂ɕς��̃e�B�b�V�������S�ɂ͂���A�o���̃r�j�[�������̃e�B�b�V�����o���̊O�ɗ��܂�悤�Ɏx���ė�������B���̒��ł͎��̃e�B�b�V�������������ŏ�̃e�B�b�V���ɂ������Ă���A���ꂪ�J��Ԃ���邱�ƂŃe�B�b�V���͈ꖇ���o������o�Ă���B