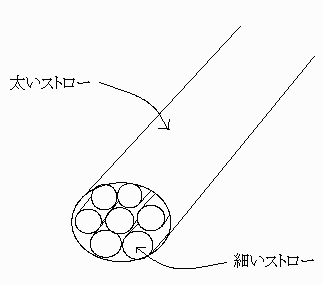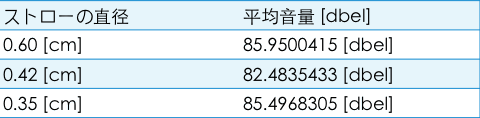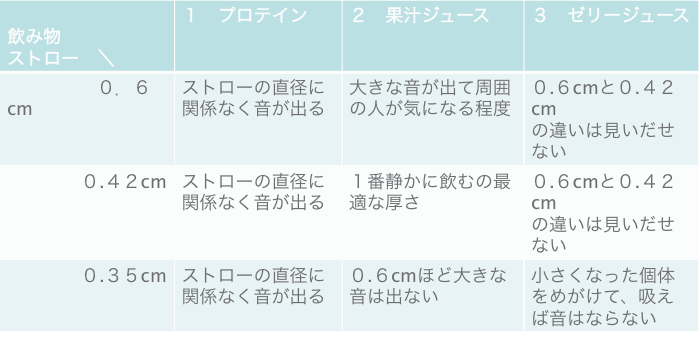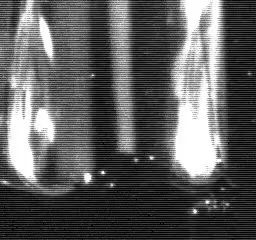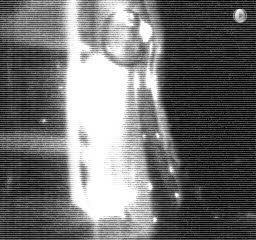ストロー実験
2013年度 物理学の基礎と概念 自由研究
グループ6
大城美樹
喜多晃康
藤根鈴香
山下百優
バージャー心エル
指導教員:岡村秀樹
研究の目的
ストローで飲み物を飲んだ時に最後のほうになると音が鳴る。
その音が鳴らないようにする方法があるだろうか?
そこで、このような音がなる理由を調べることにした。
イントロダクション
まず、ストローの原理であるが、圧力差を利用して液体がストロー内を上方に移動する。文献1の、ストローでコッ
プの水を吸い上げる原理の解説から一部を抜粋する。
 「吸
い上げるというと、「マイナスの圧力」みたいな気がしますが、違います。圧力というものが「押す」のであるのに、「吸う」のだから向きが逆で「負の圧力」
のような気がしてしまうのです。でも、負の圧力というものはありません。「水を吸い上げる話」でも圧力の大小を比べるだけで、マイナスの圧力は登場しませ
ん。
「吸
い上げるというと、「マイナスの圧力」みたいな気がしますが、違います。圧力というものが「押す」のであるのに、「吸う」のだから向きが逆で「負の圧力」
のような気がしてしまうのです。でも、負の圧力というものはありません。「水を吸い上げる話」でも圧力の大小を比べるだけで、マイナスの圧力は登場しませ
ん。
コップの水の表面を大気圧が押します。流体(この場合は水)に加えられた圧力は流体中のいたるところに同じ大きさで伝わる、というのがパスカルの原理で
す。
そこで、ストローの中で、外側の水面と同じ高さに「仮想面」を考えます。この仮想面は重さがなくてしかも丈夫なものと仮想します。すると、大気圧はコッ
プの水の中を伝わり、仮想面を下から大気圧と同じ大きさで押します。
仮想面を上から押す圧力P’は、口の中の圧力P1とストロー内の水の柱が落ちようとして生じる圧力P2の和になります。
P’=P1+P2
P=P’のとき、ストローの中の水は一定の高さで止まります。P>P’のとき、本当は大気圧が水を押し上げるのですが、主観的には、口で水を吸い上げる
ことになります。
さて、冒頭で確認したように、圧力は深さだけで決まります。そこで、水の密度をρとすると
P2=ρhとなります。ですから
P’=P1+P2=P1+ρh
ストロー中の水面が止まっているならば、P=P’ですから
P=P1+ρh であり
P1=P-ρh
となります。
これは、口の中の圧力は、水の柱によって生じる圧力の分だけ大気圧より小さい、ということを表現しています。
普通の10~20cm位のストローで意識することは余りありませんが、ホースで水槽の水を吸い上げる、などということをすると、水の柱の高さが高くなっ
てρhが大きくなるので、口の中の圧力P1を小さくしなければならなくなり、大変な作業になります。チャンスがあったら試してみてください。」
先行研究の調査では、文献2 の「音が出ないで飲み物が最後まで飲めるストロー」の1つだけが見つかった。そこから、図と説明文を転載する。
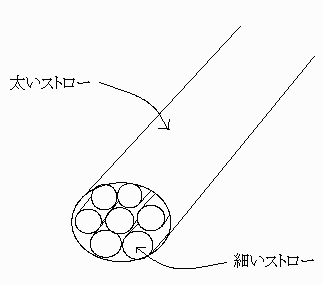
「太いストローの中に細いストローを数本入れることで,飲み物を飲み終わる際の「ズズズズ・・・」という音がでないように工夫している。」
実験1 - ストローの直径と「ズズズ・・・」の音量
文献2より、ストローの直径が細くなれば音が出なくなる可能性が示されている。細いストローでは据える量が少なくなるのでそれを補う為に
複数本を束ねたというのが、文献2の趣旨だと考えられるので、本質的には、1本でも同じ結果が得られるはずである。そこで、直径の違うストロー数種類で実
際に吸ってみて音を比較した。音量は、音圧レベルを測定することで比較した。
実験方法:直径 6.0 [mm], 4.2 [mm], 3.5 [mm] のストローで8回ずつ音圧レベル(音量)を測定。
実験結果:
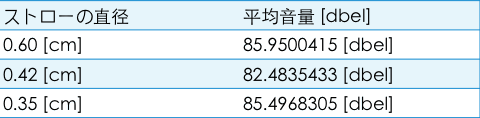
この実験では、直径と音量との関係性は見いだせなかった。
この実験で使用したストローは直径に大きな差がなかったが、直径に数ミリ以上の差があるストローで比較してみれば違いがあった可能性もある。
実験2 - ストローの形をかえてみる
ストローの形を切断面が楕円形→円形にかえてコップの水を吸い上げる
結果→水が同じくらいの分量になった時どちらも同じように音がなる
ストローの先端に切り込みをいれる
結果→上記と同じ
以上のことから、ストローの切断面の形状と吸い上げの音には関係は見いだせなかった
実験3 - 粘性の高い液体ではどうか?
1プロテイン 2果汁系ジュース 3ゼリージュース(ドロリッチ)などで音に違いがあるか?
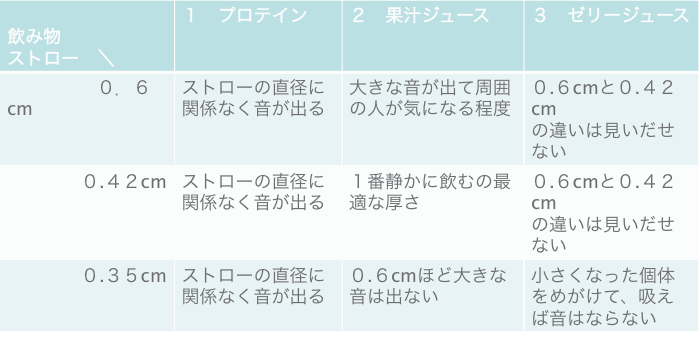
少しドロっとしたフラペチーノ(ホイップクリーム、ナッツアーモンドシロップ)を吸うと・・・
やはり音がなる
観察で気づいたこと:最後に吸い上げる時に丸いストローの先端が楕円形につぶれる。(大きい圧力がかかっているようだ)
実験4 - 容器によって違いがあるか?
ビン、プラスチックカップ、紙カップ、 コップ、で試してみた。
結果 → いずれの場合でも、中身が少なくなると音がしはじめる
実験5 - 水の動きの観察
水に黒ごまをいれて水の動きを観察した。
結果→水が多い時は変化がないが、水が少なくなると、ストローの周りに円形をなして黒ごまが集まり始める
水はストローの周りに集まるようにして動く?
これまでの実験のまとめ
→容器、ストローの切り口、液体の粘性に関わらず音はなる!
ストローの直径と音の大きさには今回の実験では関連は見いだせなかった。
実験をしていて気がついたが、液体を吸い上げ続け、液体がなくなって吸い上げることをやめるとストローの先端から気泡が出てくる
→ストローの中に空気と液体の両方が入っていて、液体の下に空気がある。
ストローの中の、空気の上の液体部分の振動とズズズ音は関係があるのかも?
高速度カメラを使った実験
以上の結果を踏まえ、ストローの中の、空気の水の部分の振動を調べた。
1. 液体を吸う様子→ストロー内で一瞬液体が戻る
http://olcs.icu.ac.jp/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28354
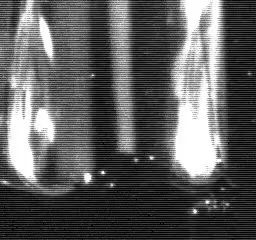
2.条件を変えて撮影(粘度の高い液体)
ジュレ、ヨーグルト
→いずれもストローの内側に空気の層ができて音がなるが、水と比べて空気の層ができにくい。空気の層が最もできにくかったヨーグルトは、音がなる頻度が少
ない。
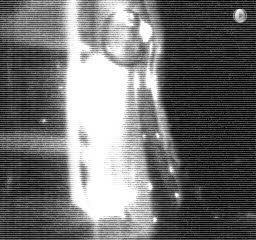
http://olcs.icu.ac.jp/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28622
やはり、ストローに空気が入るから音がでるのか?
空気と音の実験
液体の中にストローをさして吸うだけでは音は鳴らない
→空気と水が触れ合うことで音が鳴る?
そこで水面上と水面から上げた状態で吸う→音が鳴る。
次に上と同じ状況のもと、ストローの長さを変えて「水+空気=音の出方の差」を観察。
(ストローの長さ:16cm, 8cm, 6cm, 4cm)
ストローの長さに関係せず音は出るが、空気の入る量の差により音の鳴り方が変わる。
またヨーグルトを水面上と上げた状態で吸ってみたところ、吸いにくいが音は鳴った。
⇒水と空気が接触して音が鳴る!
⇒空気の層の数で音の鳴り方が変わる!
結論
実験から分かったこと → 液体と空気が両方ストローに入
ると層ができる
(飲み物の濃さによって層の間
隔が変わるが、どんな飲み物で
も層ができる)
空気と液体の層ができると → 必ず音が鳴る
最後まで飲み切るなら → 音を立てずには飲めない
音を立てずに飲むには → 飲み物と空気の層ができ始める
前に飲むのを止める
反省点
細かい実験方法の統一(測定、吸い上げ続ける時間etc)
参考文献
1) 理科おじさんの部屋 水の柱の高さと圧力 Part1
http://homepage3.nifty.com/kuebiko/science/freestdy/WtrClmn.htm
2) 千葉市教育センター(自由研究)音が出ないで飲み物が最後まで飲めるストロー
分 類:家事・雑貨 キーワード:ストロー
年 度:平成9年度 受 賞 :県展優良賞
学校名:花園中学校 学 年:1年 形 態:個人
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/db/rika_cd/jiyuken/kuhuu/genre/20902j.htm
(リンク切れ-2017年確認)
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/data/db/rika_cd/jiyuken/kuhuu/keyword/20902k.htm
 「吸
い上げるというと、「マイナスの圧力」みたいな気がしますが、違います。圧力というものが「押す」のであるのに、「吸う」のだから向きが逆で「負の圧力」
のような気がしてしまうのです。でも、負の圧力というものはありません。「水を吸い上げる話」でも圧力の大小を比べるだけで、マイナスの圧力は登場しませ
ん。
「吸
い上げるというと、「マイナスの圧力」みたいな気がしますが、違います。圧力というものが「押す」のであるのに、「吸う」のだから向きが逆で「負の圧力」
のような気がしてしまうのです。でも、負の圧力というものはありません。「水を吸い上げる話」でも圧力の大小を比べるだけで、マイナスの圧力は登場しませ
ん。