人間中心の科学(Anthropocentric Science)か?
人間中心の宗教(Anthropocentric Religion)か?
神中心の科学(Theocentric Science)か?
神中心の宗教(Theocentric Religeon)か?
吉野輝雄
SIS 2009 My final paper 「私のコミットメントは何か 」 |
科学(Science)をS、宗教(Religion)をR
として、まず相互の関係を整理してみる
と、下のようになるだろう:独立、対話、混合/対立、包含、分化という関係である。

「独立」は、互いに干渉しないで、それぞれの立場でそれぞれの生き方をすれば、不
必要な対立や争いが避けられ、それぞれが幸いであるという考え方である。
「対話」は、それぞれの立場を尊重し、対話の関係(良いものを交換し、互いを支え
るという意味も含める)にあることが望ましいという考え方である。
「混合」あるいは「対立」は、お互
いが未分化で、入り交じっているためにそれぞれ
の現代化(進化)をさまたげ、時に対立を生み出すような場合である。
「包含」には、宗教が科学を包含する関係と、その逆の関係があり得るが、ここでは
前者とし、後者は、時代とともに科学が宗教にとって代わるという考え方という意味で
「分化」とした。
そこで、それぞれにAnthropocentric (A)かTheocentric (T)を
当てはめてみた(適切か
どうか確信がないので、異論があればご指摘を)。
まず、時代と共に自然観(科学)、人間観が変化し、その影響を受けて宗教の意味も変
化して来ていることを考慮しなければならない。大昔、人間は、自然界の水や石に神が
宿り、雷や嵐などの自然現象を神の力によるものと考えていた。このようなアニミズム
(汎神論)の時代と、自然のしくみが解明されている現代とでは、人々の宗教に対する
考え方が大きく変わっているのは当然である。裏を返せば、科学の力が自然現象の説明
だけでなく、科学に基づく技術の進歩が人間生活の隅々まで入り込んで来ているために、
宗教の出番が狭まっているのが現実である。それでは、宗教は現代において、もはや意
味のないものなのだろうか?以下に私の意見を述べる。
「独立」の考え方は分かりやすく、「混合」の
ような理性の不徹底の姿勢や、不合理と
分かっていながら現実生活を動かしている宗教の力を容認するような姿勢に対する批判
も込められている点が評価できる。また、そのような妥協的姿勢は、一度問題が生じる
と非生産的な「対立」を生み出す危うさをも批判の目を向けているよう点も評価できる。
しかし、「独立」は、取り方次第では“現実逃避”の危険性を孕んでいる点を指摘しなけ
ればならない。 Conflict(衝突)をさけようとして孤塁を守ろうとするとダイナミック
な活力と成長が止まるとよく言われる。一時的に衝突があっても、対立、憎悪に発展し
ないように衝突の本質を見極め、「対話」によって相互のスタンスを見つけて行くことを
諦めてはならない。つまり、衝突をnegative に捉えるかpositive に捉えるかで、対立か
成長のどちらかに分かれてしまうことに注意する必要がある。
どちらの結果になるかは、科学(S)と宗教(R)の自立性 (independence)次第だと思う。
すなわち、内側に向いたisolated independence (孤立性)ではなく、外側に向いた
mature independence (成熟した自立性)であるかが決め手になる。互いを高め合い、生
かし合う関係を現実社会に実現しようとするあり方が「対話」型である。人間中心 (A)
か神中心 (T)のどちらにcommit しようと、それぞれが過去(歴史)の失敗や抗争に拘
泥せず、絶えず変化して行く世界の中で、新しい姿 (Vision)と使命(Mission)を探りな
がら「対話」して行くことが理想的な関係と言えよう。
「包含」について:人知を超えた超越者との関係を特別に重視する人は、科学(S)は宗
教(R)の中に含まれると考え、宗教の教典に従った自然観、人間観を基準にして自然と社
会を見る。そのような人は、信者の間では信心深いと尊敬を受けるかもしれないが、様々
な考え方がぶつかり合う開かれた社会では、現状維持思想として機能する。宗教を固定
したものと考え、科学の発展や科学によって新たに解明された自然現象に対してダイナ
ミックな対応(関係)を築いて行く努力を怠ると、どんなに深い思想をもった宗教も膠
着化して行く。時代を超えた宗教の本質に立って、絶えず変化する現実社会に建設的に
関わっていくことを、「包含」型の人には期待したいと思う。
「分化」について:この訳に違和感を覚える人がいるかも知れない。細胞分化の過程
を思い浮かべて頂きたい。1個の生殖細胞が分裂を繰り返していく過程で、ある細胞は
視覚細胞に、ある細胞は聴覚細胞へと分化して行き、分化した細胞の総体が現実の生命
活動を担っているのが個体(人間)だ。初期の段階では、周囲の環境の実態も分からず、
ただ生命維持(survival)と成長に懸命だ。それは、科学的な考え方(S)が未成熟で、すべ
てを超越者の思いのままと受身で考えていた時代(アニミズム)に似ている。しかし、
人間が、衣食住の基本条件を整えることができ、文明を築く頃になると、宗教(R)は、儀
式→教典→共同生活の規定(モラル)へと成熟(分化)し、同時に、自然のしくみを理解
し利用する技術(S)も発展(分化)して行った。その過程で、人間生活における科学(S)
の範囲と影響力が大きくなり、旧来の宗教(R)の占める力が弱まって行ったのは当然の成
り行きだと思う。この変化に基づいて、R とS の関係を捉えている人が「分化」型であ
る。理学科の学生の多くは、この型の考えを持っているのではないだろうか。主観にと
らわれずに客観的な物の見方、考え方は、成熟した近代民主主義社会では最も一般的な
考え方であるので、当然であり健全と言えるが、それでもなお私は、科学(S)を過信すべ
きではない、と考えている。
私の直感がそう言わしめているのだ(直感なので主観にとどまっている未分化人間で
あることを証明しているのかも知れないが)。その理由を一言で言えば、科学(S)は私と
いう人間に生きる力を与えてくれなかった(くれない)という経験と直感である。科学
(S)は、最終的にはエゴには勝てない、人間のエゴを正当に方向づける力は科学(S)には
ないと私は考える(あると言えるならば、ぜひその考えを聞かせて頂きたい)。科学(S)
には私の生命(人生)を託せないというのが私の本音だ。
これまで何度も言って来たが、私は科学(S)が好きだ。科学(S)は私の自然観、世界観
を広げてくれた最良の友だ。科学(S)には社会を変え、未来を拓く大きな力がある。科学
(S)の考え方(方法論)は人間の歴史の中で獲得して来た最高の知恵(文化)だ、と私は
考えている。また、これからの民主社会を支え、環境問題を解決するための基本的思想
になると考えている。しかし、科学(S)そのものには、地に着いた“足”がない --- 科学
(S)に足を付け、地に着かせるのは人間だ。科学(S)は人間の営み(業)だからだ。人間
の業である故に、科学(S) そのものは人間存在の根拠、生きる意味を与えることができ
ない、と私は考えている。
では、そう言うおまえは宗教(R)と科学(S)をどう考えているのか?と問い返されるだ
ろう。逃げるワケにはいかないので、現時点での私の考えを以下に述べる。
下の図を見て頂きたい。
中心に私がいて(self-centered)、私と関係する人間の営みを6つの円で示してある。
すなわち、
(R):超越者との関係、人との関係の中で人間としての生き方を追求する営み。
(S):自然の本質を理知によって追求する営み。
(技術):科学(S)の成果を人間生活に応用する技術。
(論理):人間の論理性を展開する営み。
(美術):人間の美的感性を表現し鑑賞する営み。
(音楽):人間の音楽的感性を表現し鑑賞する営み。
(スポーツ/身体運動):人間の身体能力を追求する営み。
(X):人間の社会のあり方を追求・実行する営み(政治、経済、教育など)
これらの営みは、当然のことながら「私」だけの営みではなく、すべての人間に関わ
るものであり、一人ひとり違ったスタンスで関わっている。その総体が人間社会であり、
全てAnthropocentric(人間中心)の営みである。そのために、時代により、地域によ
り、人により様々なかたちをとるのである。
これらの人間の営みは、神が造られた(少なくとも人間が造ったものではない)自然
の中で行われている。太陽系第三惑星・地球には、たまたま大量の液体の水が存在して
いたために特異な自然環境ができ上がり、人間を初めとする多様な生物の生存が可能と
なった。その中でも人間は、地球の歴史 (46 億年)の中で、たった数100 万年前(1/365
以下)に現れたにもかかわらず、地球を我が家のように我が者顔でわがままに使っている
のが現状だ。生き延びるためだと言われるかも知れないが、母なる地球は、我がまま息
子・人間のふるまいを見て泣いていないか?そう、やんちゃながら建設的なこともやっ
て来たのも事実だ。山を削り、地を耕し、農産物を自在に生産し、大勢の人が集団で住
める都市を築き、水を貯め、水を家々に引いて暮らしやすい生活環境をつくって来た。
そして、今やっと地球の危機的状況に気づき、地球環境をまもるための行動を始めてい
る。問題は、70 億人を超える人間が存続できる環境がいつまでもつのかである。その鍵
を握っているのは誰か?人間中心の科学にcommit すると表明した人は、それは自分た
ち人間の責任だと言うだろう(言わなければならない)。しかし、絶滅の責任までとれる
のだろうか?絶滅を防ぐ知恵と力をどうしたら結集できるのか?私も他人事にせず結集
する一人になりたいと思うが、果たして人類は2100 年を迎えることができるのかと、
悲観的になってしまうのだ。この悲観論を吹き飛ばす知恵、政治力をもった人物の登場
を期待したくなるが、このような考えは100 年前にM. Weber が批判したもので、その
結果は歴史が教えてくれている。21 世紀の現在は、すべての地球市民が目覚めなければ
良い結果は生まれない。ここに悲観論の巣がある。
人間は自分たちの未来について建設的なビジョンをもっているのだろうか?「ビジョ
ンのない民は滅びる」、という諺がある。しかし、仮に人類が絶滅したとしても自然は自
然のままである(人間に傷つけられた自然は、自然科学が教えてくれているように再生
能力があり、人間のいない別のかたちで再生するであろう)。滅びの道に落ちないために
今何をすべきなのか?大問題すぎて考えるのも空しい感じがするが、現実の問題ではな
いだろうか?人間は、自分たちがこの地球自然の中で生き延びることができ、かつ、他
の動植物と共生できる新しい自然とのつき合い方を創り出すことがこれからの基本課題
だと言っておきたい。
私も人間の一人として同じ課題の前に置かれている。しかし、すでに表明したように
私は、Anthropocentric Science にはcommit しない。私は、科学を越えたところ人間
(私)を見たいと思う。すなわち、人間は自然の中に置かれた存在であり、自然に生か
されて来たことを忘れて自然の奴隷のように扱ったり、我が物のように扱うことは許さ
れないと考える。少なくともその事を自覚しながら生きていく必要があると考える。だ
からTheocentric であるべし、と言いたいのではない。宗教を信じる者がすべて
Theocentric であると見なすのは間違っているからだ。誤解を恐れずに言えば、この世
の宗教の実態から判断する限り、すべての宗教(R)はAnthropocentric である(図の中で
R を人間サークルの中に入れているのはそのためである)。人間がいかに生きるかを追求
する営みが宗教であるとすると、時代や地域によって様々な宗教が生まれるのは必然だ。
そこで、見えざる超越者の存在と力を信じ、それを宗教儀式として表現するところで違
いが現れる。いずれの場合にも超越者への信仰が基本となるので、場合によっては、非
合理的な考え(教理)が人間の判断・行動に影響力をもつことになる。つまり、議論に
よっては正否の決着がつかず、科学的な部分証明例や体験的事実も効力をもたない。し
かし、一つの宗教(R)を絶対化せず、人間(精神)の多様な営みこそ重要だと考えれば、
互いに尊重し合え、対立がなくなり、それぞれの幸せ追求のしかたを認める生き方がで
きるのではないか。これが宗教間の終わりなき対立を解消する民主社会おいても有効な
妙案ではないかと言う人がいるかも知れない。
しかし、ここには退っ引きならない重大な問題が横たわっている。宗教(R)を
Anthropocentric なものと考えるということは、人間が超越者(神)を造ったことを認
めることになるのだ。自然と人間を造った神は、この人間の考えを許すだろうか? No!
と、私は信じる。神は神であるからだ。人間は神ではない。人間が人間のために造った
神は決して神ではない。神は、人間の理知ではとらえられない、まさに超越者だ。人間
は神に造られた存在であることを認めることが、神と人間との関係の基本である。これ
は宗教(R)を越えた原理のようなものである。私は、このような超越者(神)に自分の生
命(人生)を託す。神を図に表すことが不可能なので、図において神を人間社会をとり
囲む点線円としてあえて表していた。神の業を神の業として畏れ、人間が隣人と自然と
の関係性の中に生きる存在として、その時代、その場のニーズに応えながら生きること
が科学(人間の知的営み)のはじめである、と私は考える。
これから神中心の宗教 (Theocentric
Religion)、人間中心の科学(Anthropocentric
Science)、宗教中心の科学(Theocentric Science)について自由な考察をしてみたい。
また、文化との関係についても少し考えてみたい。
歴史上、「神中心の宗教」を熱心に追求した民族があった。イスラエル人だ。イルラエ
ル人ほど熱く神を信仰し、生活の隅々に至るまで神の戒めを守ろうとした民族はいなか
ったのではないか。旧・新訳聖書に記されている彼らの歴史と信仰の内実を見ると、そ
の熱心さに圧倒される。彼らは、なぜそれほどまでに宗教に熱心になったのか?なろう
と努めたのか?そして、その結果は?
イスラエル人の信仰の父は、アブラハムである。アブラハムは、神の命令と約束を信
じ、何不自由のない遊牧の地ハランから見知らぬ所へ出て行った、と創世記に記されて
いる。神からの約束とは、子孫を星の数のように増やし祝福するというものであった。
アブラハムは、まさに神中心の生き方を貫いた人間として、今も全てのユダヤ人に尊敬
を受けている。しかし、アブラハムも完全な人間ではなかった。それは、子どもができ
なければ神の約束が実現しないのに、なかなか子が授からない事に焦りを感じ、妻サラ
の勧めもあってハガルという側女に子を産ませるという過ちを犯してしまったのだ(こ
れが、今に続くアラブとイスラエルとの対立の源と言う人がある)。
アブラハムとサラの間に生まれた息子イサクに双子の兄エサウと弟ヤコブがいたが、
ヤコブは兄をだまして長子の権利を手に入れるというズルい人間であった。しかし、そ
の罪の重さにおののき、夢の中で神の使いと格闘した時、“赦し”が与えられるまで御使
いの足を離さなかったという内的体験を語っている。そして、和解を願い、何十年ぶり
かで兄エサウと合うために出て行った時にも恐れがいっぱいであったが、最後に兄から
の赦しが得られた。そして、最期には12 人の子供たちを部族の長に据え、神からの赦し
の中で安らかに死んだ。
イスラエル人(ユダヤ人)は、アブラハム、イサク、ヤコブの3人の先祖に特別な敬
意をはらい、「アブラハム、イサク、ヤコブの神」と言って神を呼ぶ。そのような偉大な
先祖であったが、現実には3人とも人間的には弱さと限界をもった人間であった。神の
前に完全な人間はいないという人間観がここにある。
その後、イスラエルの民は、当時の大国エジプトの奴隷となった。その奴隷から民を
率いて約束の地カナンに導いたのが、モーセである。イスラエル人60 万人とリーダーの
モーセは、この時エジプト脱出(Exodus)という大きな歴史的体験を共有する(映画「十
戒」で有名)。カナンまでの道は40 年にわたる荒野の旅で、神の護りの中の旅でありな
がら、飢えへの不安、内部分裂、不信、迷走の繰り返しであった。そこで、荒野の旅は
よく個人の人生にも対比される。この旅の途中、モーセは神から「十戒」を授かる。す
なわち、1-5 戒までは神への信仰に関する掟であり、6-10 戒は人と人との間に関する掟
(倫理)であった。(新訳聖書の<マタイ22:37>は、その400 年後イエスによってな
された“現代的解釈”である)。この掟は、人を規定(律法)によって縛ることが目的で
はなく、人間が人間らしく生きるための基本を示したものであった。神は、人間がこの
掟を知らなくても自分の意志で掟に則った生き方をすることをよしとするほど寛容であ
った(ローマ人への手紙 2: 14-15)。しかし、イスラエル人は、十戒が自分たちに与え
られたことを誇りに思い、神に選ばれた民として厳守しようと熱心に努めた。ここから
Theocentric Religegion を追求する民としての歩みが始まったのである。
しかし、悲しいかなイスラエル人の宗教的熱心さをもってしても、人間的弱さの故に
十戒をまもり通すことができなかった。そこで民はどうなったのか?経済的に豊かで、
神への信仰に熱心であろうとした人たちは、神殿での礼拝を忠実に守ろうとし、貧しく
生活することが精一杯で礼拝を守ることができない人たちは、罪人として社会から退け
られて行った。もちろん中には、儀式的な礼拝に流されず、アブラハム以来の真の神へ
の信仰を生活の中で実行していた人もあった。このようなAnthropocentric religion に
陥っていた時代に生まれたのがキリスト・イエスである。イエスは、十戒(律法)の真
意を生き方で示し、同時に社会から落ちこぼれ、自らを神から遠い者と決めつけていた
「失われた人々」に近づき、生きた言葉と行動で神の意志と愛を証しした。
しかし、その行動は、イエスに従っていた12 弟子によっても十分理解されなかった。
弟子達は、神殿で神の律法を説く宗教的指導者とは違う真の人(ひとの子)イエスを3
年間も近くで見ていたにも拘わらず、神の意志を悟ることができなかったのだ。それは
イエスが十字架刑になった時に顕わになった。ユダの裏切りによって、イエスが逮捕さ
れ、裁判の結果、神冒涜罪で十字架刑を言い渡された時、弟子の筆頭ペテロは、「わたし
はイエスなど知らない」と裏切ってしまったのだ。実は、残りの10 人の弟子たちも皆、
イエスを見捨てて逃げ、ペテロと同じように人間的弱さを露呈してしまった。
Anthropocentric religion の結末がそこにあった。実は、キリスト者の大部分は、この
12 弟子と同じ弱さ(罪)が神の前で露わにされた人たちである。そのようなキリスト者
は、世界に数多くあるAnthropocentric religion を批判する資格をもたず、同時に
Anthropocentric religion の危うさを知っている人たちである。
ところで、自殺したユダ以外の11 人の弟子たちは、その後どうなったのか?敗者とし
てひっそりと生涯を閉じたのか?それが裏切り者の末路であるような事例は歴史上、枚
挙にいとまない。しかし、ペテロやトマスなどの場合は全く違った。新訳聖書の4つの
福音書の最後の章と使徒言行録のはじめの数章を読むと、彼らに何が起こったのかが分
かる。それは、まさにGodcentric な出来事であった。そこに社会的飾りを無くした生身
の人間が出会った時に起こる体験が記されている。その記述を客観性のあるものと見る
か、宗教的プロパガンダと見るか2つに分かれる。少なくとも理性的理解の及ばない
Godcentric な事なので、現代人の9 割以上の人は受け入れないであろう。しかし、キリ
スト教信仰の本質がここにあるのだ。ここに記されている証しにyes と言える人が、キ
リスト者として生きることを人生の軸としている人である。
これまで述べたようにアブラハム、ヤコブをはじめイエスの弟子も、イスラエル人の
多くも、神への信仰に生きた人たちであるが、誰一人人間的に完全な人はいなかった。
換言すると、罪人という現実を背負った人ばかりであった。それ故に神から裁かれ断罪
されても仕方のない人間であったが、その罪に向かい合い、告白した時に初めて神との
出会い(救い)を経験したのであった。救いの結果は何であったか?一言で答えるのは
難しいが、あえて言うならば、「自分があるがままの自分として神に受け入れられている
ことの幸いと安心を実感できるようになった」という体験と言ってよいと思う。救いは
極めて個人的な出来事であるのだ。しかし、それが、Godcentric なところで起こった場
合には、その人を変え、周囲を変える力になる。「30 倍、50 倍、100 倍の実(命の通
った人との関係に生きる力が神から与えられ、人との関係を築く業という実)を結ぶ」(マ
タイ 13:8 の私訳)という神の業が始まるからだ。
ところで、このように神への信仰を第一にするイスラエル人の自然観はどのようなも
のだったのだろうか?聖書は、18 世紀に自然科学が成立する1700 年以上前に書かれた
書物であるので、われわれにとって常識の「自然科学の方法論」に従って自然を観てい
ない。しかし、彼らの自然を観る目は鋭く、繊細で、自然への畏怖に満ちている。自然
は神によって創造されたという揺るぎない信仰があったからだ。その一端を、詩編104
編と創世記から読み取り、仙川キリスト教会で話したことがあるので、紹介したい。
(次のウエブサイトを参照下さい。http://www.sengawac.com/sengawaA/m080817.html)
Anthropocentric Science は20 世紀以降の現代科学だと私は考える。それが、
anti-Theocentric(反宗教)かnon-Theocentric(非宗教)かはその人の立場によって
違う。ところで、ドイツの哲学者ニーチェは『ツァラトゥストラはかく語りき』, 1885)
の中で、「神は死んだ」という衝撃的な表現を使った。その部分を引用する;
「兄弟たちよ、私は君達に切望する、大地に忠実であれと。君達は地上を超えた希望
を説く人々を信じてはならない。彼等こそ毒の調合者である。 かつては、神を冒涜す
ることが最大の冒涜だった。しかし神は死んだ。そして神とともに、それら冒涜者達
も死んだのだ。」
彼は何を言おうとしたのか?私は、ここで哲学的議論をしたくない。代わりに大胆な
解釈を試みる(笑ってくれてもよい)。真意は、「おまえの世話をしてくれる親はもうい
ないと思え。自立した人間として現実に向かい合うのだ!」ではないのか。もう少し砕
いて説明しよう。「もう大人になったのだから、これからは自活して生活費を自分で稼ぎ、
仕事も自分でさがし、他人から信頼されるようしっかりと生活しなさい。すべて自力で
道を切り開いて行け」と言われたらどうするか?ひどい親だと恨むか?それは甘えだ。
20 年近く、衣食住の心配をせず、社会のしくみや生活の基本(読み書き計算力/リテラ
シー)を身につけるために学校に行かせてもらったのだから、もう親に甘えるのを止め
自立しなければと考えるのが成熟した人間ではないのか?確かに、科学する力(自然の
しくみを知る力)が未熟で、乏しい科学の知識で衣食住を豊かにする知恵も生活力も足
りなかった時期は、不安や不足を親(神)に訴えれば、愛情ある親(神)が応えてくれ
ていた。今や、そこから巣立つ時が来たのだ、と親(神)が伝えようとしていたのでは
ないか。ところが、我がままで粗暴なおまえは、これまで育ててくれた豊かな自然を破
壊して省みない生活を送っている。これはどうしたことか。それが自立した人間の生き
方か。私(親/神)はおまえの見えない所で生きている。しかし、もう加護はしない。
これからは、親の加護に頼らず自分の頭で考え、自分の責任で現実も課題に向かうのだ、
と言っているようだ。これが私の解釈である。ニーチェはもっと徹底していて、現実を
見ないで天国への希望を説く教会に従うな、大地(現実)に忠実であれとまで言ってい
る。
ここでニーチェさんへ一言:現実に向かい合って生きるべしと
いう哲学には共感するの
だが、「神は死んだ」という論は受け入れられない。その理由は、ニーチェさんと言え
ども、神が死んだか生きているかを知ることはできないからだ。「私は、神は死んだと
信じる」と言ってほしかった。苦悩し、考察した結果、そう信じるのは自由だが、こん
な激しい言い方をすると、生きることが精一杯の弱い人を惑わすことになる事を想像で
きなかったのか。それでは哲学者として失格ではないか。神が生きていると信じるかど
うかは、今も一人ひとりの自由であり、科学で証明できないことなのだから。
核兵器を蓄積し他国を威嚇して外交力を行使している国が、仮に核兵器製造工場が爆
発して放射能汚染を引き起こし多数の人が死亡したとする。そこで自立した人間は、“な
ぜ神はわれわれの生命を守ってくれなかったのか”と言わないだろう。同じように、環
境汚染によって人間が滅びる危機に直面したとしても、それは人間の責任だ。当然のこ
とである。当然のことをあえて言わなければならない理由は、“不都合な時に”神のせい
にする人がいるからである。それは、“都合のよいように”神の名を使うのと同じことだ。
要するに、無神論者ならぬ不神論者の考えである。Anthropocentric Science を表明す
るならば、科学の成果も害(リスク)も丸ごと引き受けなければならない。そして、リ
スク回避の方法を、科学、技術、政治など人間の知恵の総力をあげて考える必要がある。
他人まかせにしない自立した市民として社会的責任を担う者でなければならない。誠実
なAnthropocentric Scientist は、おそらくそのように考えるであろう。
問題は、科学の成果を最大限に享受しながら、環境破壊につながる行為を改めようと
しない人たちの存在だ。地球市民の存続を危うくするのは、そのような人たちではない
か?科学の力で行動を変えるよう説得できるのだろうか?科学そのものにはその力も責
任もない。責任は科学を担う人間ではないのか。その人間の意識と行動を変えるにはど
うすればよいのか?Anthropocentric Science 者たちの意見を聞きたいと思う。しかし、
Anthropocentric Science 者でなくても答えるのが難しい命題である。
現実の問題に対する認識と対応法については、Anthropocentric Science 者と変わら
ない、と私は思う。ただ問題の原因を神のせいにしたり、解決を神まかせにすることは
決してしないだろう。神の存在を信じているが、物事の因果関係は自然と社会のしくみ
によって決まると考え、自然の中に置かれた存在として、また、社会との関わりの中で
何ができるかを神に尋ねつつ、知恵を尽くし、協力しながら生きていくだろう。つまり、
外から見る限り社会的行動様式は、Anthropocentric Science 者とさほど違いがないだ
ろう。
では、なぜ 神中心(Theocentric)であろうとするのか?究極の答えは、神が生きて
いるから、となるであろうが、信仰者によって答え方が違うと思う --- ある人は、「私は
神との関係を自分の人生の基本に据えているから」と答えるだろう。また、ある人は、「自
然は人間の所有物ではなく、自然と人間を創造した神のものであると考え(信じ)るの
で、自然との関わり(つき合い方)を根本から考え直しているから」と答えるだろう。
また、ある人は、「人間の理性を重んじつつも、人間の欲望を制御する力は理性を超えた
ところ(理性を人間に与えた神)から来ると信じるので、理性の働きとその成果(科学
技術の産物)を絶対的な拠りどころとしない生き方をしているから」と答えるかも知れ
ない。要するに、神は人間が造ったものと考えるのがAnthropocentric Science 者で、
人間(自分)も自然も神が造られたものという認識(信仰)に立って、自然と社会に向
かい合う人が、Theocentric Science 者である。
人間と自然がどのように (how)造られたかは、永遠の問いである。全ての人がこの問
いの前にいる。それを知ろうとする営みが自然科学である。聖書の創世記は、人間が神
から造られたという信仰告白であって、科学の方法論に従って明らかにされた自然像で
はない。ダーウインの進化論は、緻密な観察と考察による一つの科学的自然像(仮説)
である。その正しさは、多くの観察データの集積によって説得力をもって述べられてい
るが、さらなる科学的研究が科学の必然として要求されている。例えば、ミクロな分子
レベルとマクロな生物種の変化を観ることによって地球における生命発生、進化の過程
が明らかにされつつある。それは完全な自然像ではないかも知れないが、理性(自然科
学)に裏打ちされている。反論するには、科学的研究が要求される。
ある国のように、聖書に記されている2500 年前のイスラエル人の自然観であり、信
仰表明である創造論をもって、近代自然科学に対して抵抗(論争)するのは、“勘違い”
としか言いようがない。創造論者が何を護ろうとしているのか私には分からない。自分
たちの信仰基盤が崩れることを恐れているのか?信じる神を護るために熱心なのか?い
ずれ歴史の一ページにそんな時代もあったと記される運命にある、と私は思っている。
少なくとも私の考えるTheocentric Science の考え方とは全く次元の異なる問題(混乱)
である。
人間中心の思想と成果とは、要するに「文化」のことである、と私は考える。その中
で有形な財産が「文明」である。すなわち、宗教、科学のように精神的、知的財産と思
想(考え方)が「文化」であり、科学技術や産物(建築物、道具、衣類、食料、材料な
ど)といった物質的なものが「文明」である。文化も文明も人間の生き方と生活に深く
関わっている。どんな文化・文明とどのように関わっているかによって、その人の内的・
外的豊かさが違ってくる。これが、人間が宗教と科学を真剣に考える根本理由である。
ここで、少し脇道にそれ、音楽と宗教との関わりについて考えて見たい。音楽の源は
何か?口から発する声、板や石を叩くと出る音、糸(弦)を弾くときの音、筒(管)を
吹くときの音などを奏で共感する(楽しむ、慰める、鼓舞する)ことから始まったので
はないか?つまり、感性をもつ人間どうしの共感行為が音楽と言ってよいだろう。(以上
は、ネットで仕入れたにわか知識で、他にも種々の説があるらしい)。科学が知性の営み
であるのに対して、音楽は感性の営みである。美術、工芸、舞踊もまた人間の感性の営
みであり、時代、場所、状況に応じて新たな感性表現が生まれて来た。周囲の人の感性
に触れる新たな作品を創り出す行為と、それに触れ感動する受け手の感性が出会い、そ
れぞれの感性がさらに磨きあげられて行く。それが音楽や美術の力であり、終りのない
永遠の営みである。
そのようなAnthropocentric な営み(action)と感動(reaction)の源泉はどこにあるの
か?私見であるが、人間が生まれ育って行く現実が、“単独”の歩みでなく、“関係”の
歩みに源泉があると、私は考える。さらに考えを飛躍させると、自然も人間も関係性の
存在として神に造られている(という宿命)故だと思う。人間は、誰一人として関係の
ネットワークからのがれることができないが、どのような関係に生きるかは自由だ。関
係を強く、豊かにしたいと願い、他者と共感する営み(action)に一生を捧げる人が芸術家
(artist)なのだと思う。その人が神を意識しているか否かに関わらず、それは優れて人間
的な行為であり、神の創造にかなった生き方であると、私には思える。
2つ目の脇道:かつて Shout というロックの歌を目の前で聴いたことがあった。まさ
に“叫び”であった。歌詞は聞き取れず、歌になっているのか分からなかった。私の感
性は、その音楽に対して拒否反応を示し始めた。その場から出て行こうと思った。しか
し、その時、待てよ、という内側からの声が聞こえた。あの若者は何を表現しようとし
ているのか?誰と共感したいと思い歌っているのか(願っているのか)考えてみようと。
そこで、若者の叫びの源を想像し始めた。当たっているかどうかは別として、孤独の中
からの叫びか、何かへの怒りか、と考えた。その中、どう表現すれば良いのか分からな
い混沌とした思いを外にはき出しているのかも知れないと思えて来た。教室では決して
見せない素の人間がそこにいるように思えて来た。歌っている(叫んでいる)若者の顔
と動きをまじまじと見て、そこから何か読み取れるものがあるか探り始めた。不思議な
ことに心の中に動くものを感じた。何をShout しているのか?彼は最近数年間、何に情
熱を向けて来たのか…と想像すると楽しくなって来た。上手に歌おうとしていない分だ
け分かりやすいと思ったりもしたが、やはり、自分のことばでShout しないと、人間は
“理解”できないと思った。何を受け取るかは聴き手の自由と言われればそれまでで、
論理を旨とする科学と違って感性表現の特性なのかも知れない。
聴覚を通じた感性の世界が音楽であるとすれば、美術は、視覚を通じた感性の世界で
ある。また、スポーツは身体表現(速さ、強さ、集中力、バランス力、コンビネーショ
ン、チームワークなど)を通じて人間性を表し、人と人との関係の美しさ、楽しさ、耀
きを共有する行為である、と言えよう。
そこに宗教の出番などない、と言う人がいるかも知れない。しかし、その道のトップ
を究めた人の話を聞くと、精神的要素がいかに大事であるかがしばしば語られる。不断
の練習、努力の裏打ちがあってのことだが、勝つことよりも自分の力を出し切ることに
目標をおいて試合に臨んでいるとか、挫折や行き詰まりの後に本当の自信がついたとい
った言葉が出てくる。それは、宗教的体験に似ている。誰にも語らない究極のところで、
自分を超えた存在との対峙があった、と言っているように私には思われた。不思議なこ
とだが、誰にも寄りかからない孤独の個として現実に向かった時、人は最も人間らしく
なれ、隣人とも自然とも甘えのない関係をつくることができるようだ。
論理の起源とは何か?かたちのない論理に起源が存在するとしたらそれは何を意味す
るのか?人間はなぜ考えるのかを探ることか?あるいは、考える機能がどこにあるのか
を探ることか?あるいは、論理性がどこから生まれ、なぜ論理的であると認識されるの
かを明らかにすることか?論理に弱い人間である私に議論する資格がなさそうだが、一
人の人間として興味がある。
17 世紀のフランスの哲学者・科学者パスカルの言葉「人間は考える葦である」は、私
の場合、人間が論理的に考える存在であることを考察する原点である。
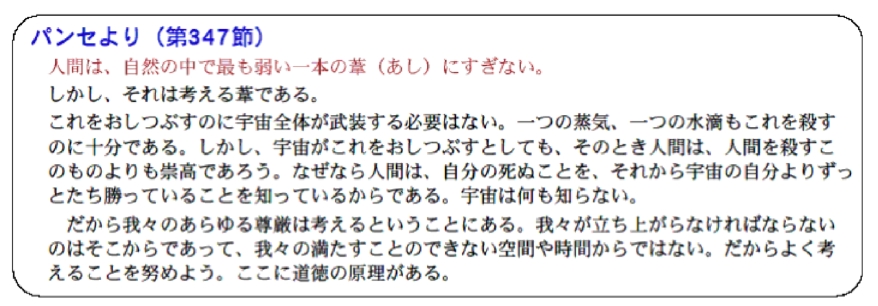
パスカルは「考えることによって宇宙を飲み込」み「宇宙は私をつつみ、一つの点の
ように飲み込む」とも言っている。つまり、考えることが人間が人間であることの特性
で、ここに道徳の原理=人間としての生き方の基本がある、とパスカルと言うのだ。論
理が生き方の基本という考えに違和感を感じるかも知れないが、私は、ここがポイント
だと思っている。つまり、論理も科学や音楽と同様に人間の営みであり、どこまでも発
展し終わりを知らない性質がある。科学が自然の本質を理知によって追求する営みであ
るように、数学は論理性の世界を広げ深めることを追求する人間の営みと言える。しか
し、論理は数学だけのものではない。科学の方法論には論理性が不可欠である、という
よりも不可分である。感性を基本とする音楽ですら、交響曲などの構成が論理的である
ものが多い。詳しくは、西洋クラシック音楽の発展の歴史をひも解く必要があるが、論
理と人間の営みについて考えさせられる事実である。
合理性の基本は、真偽の判別であると考えると、論理の起源について一つの仮説を立
てることができる。つまり、真偽を決めるのは何かという問題に対して、私は、時代と
社会を超えて決まる原理のようなものが存在すると考えるのだ。数学では、まず公理を
定め、その下で演繹的に論理を展開するのであろうが、公理の設定を許容する根拠と論
理展開の過程を承認する人間の知性の由来に私は関心がある。そんな問いに対する答え
など存在しない、と言われそうだが、やはり答えを知りたい。ここで、自然と人間を創
造した神が、この自然を動かす背後に見えざる論理の世界を置いたという説明もできる
が、これはUltra-theocentric と言うべきであろう。
知的にも感性的にも体力的にも限界のある私の考察はここで終える。きままな考察な
ので、異論、反論が多々あるかと思う。聞かせて頂けるとうれしい。
(2009 年11 月27 日)
▲ 戻る