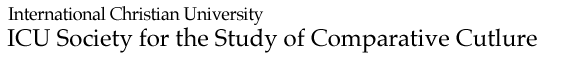
|
[日本語] | [English] |
| Home | About the Society Special Lecture |
Publications | Organization and Members |
Special Lecture for the 30th Anniversary of the Division of Comparative Culture
|
||||
|
"Three Decades of Comparative Culture: Achievements and Prospects"
Special Lecture for the 30th Anniversary, rm. A-206, January 26, 2007 |
Professor Emeritus Koichi Namiki |
I 比較文化研究科の現在1 比較文化研究科は今学年度で、その設立から満30年の歴史を刻んだ。この研究科は博士前期と後期の両課程を備えた大学院として、1976年の4月の開設が同年の2月に認可されたが、まず前期課程のみの開設からスタートした。大学院発足のためには学生募集、入学試験、開講する科目の調整などを必要とし、短期間でそれらを行ったが、4月の通常の入学式までには諸準備が完了せず、ようやく5月11日に入学式を挙行できた。6名の学生を迎えてスタートした時の感激はいまだに忘れがたい。 30年を経た現在、2006年度冬学期の総在籍者数は55名である。内訳は、博士前期課程が32名で、昨年度の4月と9月の入学者が合わせて15名、今年度が同 様に17名である。後期課程の在籍者は23名で、その内、博士学位候補資格を認められた者が10名である。私学の文科系大学院としてはかなりの規模であり、まず現在の充実を皆様とともに喜びたい。研究科長のウィルソン教授が挨拶の中で語られたように、本日はお祝いの日、セレブレーションの時である。 2 比較文化研究科はこの30年の間にどれだけの修了生を世に送り出したか。2006年3月の卒業式までの学位受領者は、博士前期(文学修士)が332名、博士後期課程(学術博士もしくは博士(学術))が45名、学位授与規定が定める期限内の博士論文の提出者で、「課程博士」と呼ばれる。そのほかに期限を過ぎて博士論文を提出して博士学位を得た者(論文博士)が5名で、博士課程に在籍した者で博士号を取得した者は合計50名である。この数も誇りうる。 3 比較文化研究科の現在は学位の授与数だけでは計れない。もう一つ大事な活動が「比較文化研究会」である。この研究会は、研究科の学生、出身者、現教員および元教員、その他の若干の賛同者から成る学内学会であり、その会員数は2006年度は153名である。規定により一定期間会費を収めないと退会扱いされるので、これだけの活動会員がいることも、研究科の大きな支えである。 「比較文化研究会」が刊行する会誌『ICU 比較文化』の最新号はNo.38(2006年3月)であり、これも研究成果の大事な集積である。 4 比較文化研究科の教員組織は教授会ではなく、「委員会」と呼ばれている。2006年度の「博士前期課程」を担当する教員は、「専任」(委員会を構成し、修士論文を指導する者)が24名、「兼担」(他の研究科の専任であるが、比較文化研究科でも講義もしくは論文を指導する者)が4名、「科目担当」(講義のみを担当) が2名である。 「博士後期課程」は委員会を構成する「専任」が21名、「兼担」が2名である。 5 博士前期課程と後期課程の責任者であり、それぞれの委員会の議長を務めるのが「研究科長」である。研究科長を勤めた教授の氏名を掲げて感謝を表しておきたい。初代は山本達郎、以降、魚住昌良、並木浩一、金沢正剛、Gerhard Schepers、荒木亨、斎藤和明、Marion Steele、小島康敬の各教授、そして現在はRichard Wilson教授で、第10代の科長に当たる。研究科長は2期4年を勤めるのが通例であるが、1期2年で交代した方、中には行政職に引き抜かれて1年のみ の方もおられる。 II 比較文化研究科の設立事情1 学内には比較文化研究科に先行する二つの研究科が存在する。「教育学研究科」と「行政学研究科」である。それらの研究科はICU設立の使命に基づいて設立された。「教育学研究科」は1957年の設立である。その母胎は「教育研究所」(創立1955年)であり、戦後の民主主義の基礎研究と教育者の養成という、ICU の設立目標の一つを学術的に深める意図をもって大学院が設立された。 もう一つが1963年に設立された「行政学研究科」である。母胎は「社会科学研究所」(創立1958年)であり、日本の敗戦を反省して民主主義国家の新しい国家行政、および国際行政の専門家を育成しようというICU の当初の課題を担って大学院が開設された。 2 これら二つの研究科に対して、比較文化研究科は設立の背景が異なっていた。ICU開設以後の学内における学問関心の勃興が、従来の国立大学の大学院とは異なる新しい学問方法論に基づく大学院作りを促した。高度の研究の必要に基づく大学院構想の母胎は「アジア文化研究所」(旧称はアジア文化研究委員会、創立1958年)および「キリスト教と文化研究所」である。この内、主導的な役割を果たしたのは、後述のように、「アジア文化研究所」であった。この研究所は歴史学の教員が主要構成員であり、ICUの開設当初にはあまり意識されていなかったアジア研究が本学の重要な研究分野であることの自覚を次第に高めた。その具体的な研究関心事は、キリスト教とアジアの接触、近代化などであり、武田(長)清子ディレクターが研究計画と推進の中心的な役割を担った。 もう一つの母胎であったのが1963年に創立の「キリスト教と文化研究所」であった。今日ではどこのキリスト教大学にも類似の研究所が設置されているが、この研究所はその先駆けとなった。「キリスト教」と「文化」の本質的な関係と両者の緊張する関係とを自覚し、この自覚を原動力とする関連学問分野の大学院を設立することが、この研究所の最初からの目標であった。設立当初は、神田盾夫(新約学・西洋古典学、人文科学科創設者)、斎藤勇(英文学)、石原謙[青山学院との兼担](教会史)が指導的な役割を担った。 3 比較文化研究科の設立は「カイロスの訪れ」の所産であるという歴史的な回顧ができる。五つの要因が整ったことが大学院の設立を可能にした。 a 先進国の大学は1969年を中心とする激動期を1960年代の後半に迎えた。大学紛争は1970年代の始めに収束したが、その沈静後に学問の再形成の意欲が胎動した。「アジア文化研究所」は早くも1971年から翌年にかけて、長清子研究所長の提唱と努力により韓国、中国、日本を比較する研究に着手して、すでに国際的な研究集会の開催などの経験を積み重ねていた。この活動による視野の拡大と問題意識の深化とともに、1972年には新しいアジア文化研究の大学院構想が芽生えた。 他方、「キリスト教と文化研究所」を構成する人文科学科は、大学紛争によって4名の教員を失い、学内でも弱体化が著しかった。この状況を打開するための一つの試みとして、思想(哲学・神学)、文学、芸術を総合できる大学院造りを模索し始めたが、教授はE. Kidder(美術・考古学)、古屋安雄(神学)のみであった。中川秀恭(新約学)が教授として着任したが、大学院造りには人的資源が不足していた。設立の期研究所を指導した神田盾夫(西洋古典学・新約学、人文科学科の創立者)、英文学の泰斗で後に文化勲章を受章する齋藤勇両教授はすでに定年を迎えており、この時期の残された人文科学科の構成員は概して若かった。大学院設立の目的を達するには、客観的に見て、学科外部の有力な分野との連携が必要であった。 b 1970年に入ってからの歴史学関係の教員の充実はめざましく、超Aクラスの教授が外部より次々に着任した。文化勲章を受賞することになる大塚久雄(経済史)と山本達郎(アジア史)の両教授、それにキリシタン研究の第一人者であった海老沢有道教授、それに学内育ちの長清子教授。この四者は新たな大学院を立ち上げる十分な実力と学問的な基盤を用意した。歴史学にはさらにアジアと西欧を研究分野とする教員が加わった。大学委員設置の実力を備えた人的基盤と内実が整った。 c アジア文化研究所の有力教授たちは、大学院の方法論として「比較文化」を選び、研究対象とする「文化」についての共通認識を築いた。大塚、山本両教授が主唱した文化理解は、一般理論、抽象的で主知的な文化理解ではなく、「実践的」かつ「問題解決的」な研究対象としての「学際的な」文化理解であった。これは研究対象の自由度を保証し、文化研究に関心を持つ幅広い研究者を包摂でき、伝統的、文献的な研究態度を採る人文科学の教員にも、文化の基礎研究者としての位置を与えうるものであった。ここに、人文科学科教員が大学紛争による弱体化を乗り越え、大学院に参加する道が開かれた。協力関係の実現は当初の「比較文化」をより豊かにするものであることが、後に証示された。 d 大学院設立には多額の経費を必要とする。幸いにもこの時期、本学の野川沿いから西南方向に広がる広大なキャンパスを東京都に公園用地として売却し、その代金を教学の充実に当てるための「創立25年基金」が1975年10月に設立された。優れた教学計画には投資的予算が計上される道が開かれた。この幸運な時期に行政学研究科の博士後期課程の設置計画が進められ、それに並行するかたちで、比較文化研究科の博士前期・後期の設置計画が進行したのである。比較文化研究科の大学院設置計画については、当時の中川秀恭学長(1975年9月に着任)の理解、助言と支援が大変大きかった。 e 教学計画と人的資源の確保だけでは、当時の文部省に比較文化研究科の設置は申請できない。研究科が新しい包括的な文化理解と学際的な研究方法に適合する学位を修了生に授与できなければならない。博士前期課程については「文学修士」号で対応できるとしても、博士後期課程の修了生に対しては「文学博士」号は適切ではなく、比較文化研究科の構想は授与すべき博士号の問題で行きづまった。しかし幸運にも、1975年に文部省は学問の専門分化に対応する博士学位を次々に新設することを防ぐため、米国のPhDに対応する、文科系各分野における知の統合の達成者に与えられる「学術博士」号の考え方を採用し、新たな学位規定を施行した。これは比較文化研究科には「渡りに船」であった。この新たな博士学位の方針に準拠した第一号が本学の比較文化研究科であった。 (この事情については、武田清子「ICU 比較文化の“学術博士”-そのヴィジョンと構想」『大学時報』1987年9月号所収、『ICU比較文化』15、1988年に再録、武田清子『未来を切り拓く大学-国際基督教大学五十年の理念と軌跡』国際基督教大学出版局、2000年、147-152頁に主要部分を再録、を参照されたい。) 比較文化研究科はこのような5要因がそろうことによって誕生したと、私は考察する。「時」が満ちて本学に与えられた新たな大学院であったとの感を強くする。 4 比較文化研究科設立に至る経緯は前掲、武田(長)清子氏の『未来を切り拓く大学-国際基督教大学五十年の理念と軌跡』139-153頁にまとめられている。ここではごく簡単に述べておきたい。 1972年頃から歴史学有力教員による大学院構想 1973年11月、学務委員会での設立計画の承認 1974年2月、教授会での承認 この段階を踏んで、1975年に「比較文化研究科設立準備委員会」が山本達郎教授を委員長として発足した。この大学院構想に人文科学科も参加を表明、当時の学科長Roger Matthewsが設立準備委員会に参加した。 「キリスト教と文化研究所」は、比較文化の可能性の探求を開始した。この時期(1975年4月~10月)に研究所は「比較文化とは何か」を主題とする 5 回の連続講演会を開催した。その内、比較の問題に直接間接にふれた講師と論題を紹介すれば、大塚久雄「比較文化をどう考えるか」、井門富二夫(筑波大学教授)「比較文化は可能か-概論構築をめぐる試論」、八木誠一「宗教の比較について」、笹淵友一「島崎藤村における『労働と文学』-藤村の労働神聖観とその軌跡」、大木英夫「比較文化の終末論的基礎づけ」(東京神学大学教授)が挙げられる。そのほかの機会に行われた講演、荒木亨「比較詩学」、および比較文化研究科の開設後に研究科の主催で行われた海老沢有道「復古神道とキリスト教」(1976年7月)を編集した論集が1977年に、山本達郎編『比較文化の試み』研究社、として出版された。比較文化研究科の設立を国内に示した最初の出版物としての意味を持った。 設立準備委員会に話を戻したい。この委員会は申請すべき授業科目の構成を具体的に検討した。委員会を主導した歴史学の諸教授は、時代とともに変化する文化の動態を視野におく。したがって比較文化研究科の授業科目は、当然ながら「文化変動論」に代表されるような「経験科学」的な授業科目が並んだ。それは「真理は変化しない」ものであり、沈思して学問の蘊奥を極めるという人文科学の哲学系の感覚にはなじまないものであった。人間の感性を問う文学系の教員には比較文化の授業科目は外の世界と感じられた。そのために人文科学科内部の参加意志が揺らぎ、設立準備委員会にそれが投影されたために、設置を推進する有力な教授たちとの間に軋轢が生じた。この状況の中で人文科学科の代表をMatthews教授から引き継いだ並木は、歴史学の諸教授たちとの信頼関係の修復にまず努めた。人文科学系の科目については、「基礎科目」群の中に、たとえば「西洋における文学と芸術」、「専門科目」群の中に「人間理解論」のようなかたちで活かすことで妥協を図り、人文科学科の教員たちの協力を取り付けた。 「比較文化研究科設置申請書」は1975年10月に文部省に提出された。その後の審査を経て、博士前期課程と後期課程の設置が1976年2月に許可された。申請の時期に森有正氏はパリ大学の教授であったが、文部省より本学の教授をも勤めることのできる兼担教授として特別に認められていた。しかし森有正氏は惜しくも開設前に急逝、比較文化研究科に着任できなかった。 5 大学院の新設は教員の努力だけでできるものではない。この時期、大学院事務室は行政学研究科博士後期課程の申請事務をすでに抱えていた。ここに短期間で処理すべき比較文化研究科博士前期・後期課程の申請事務が加わり、途方もない事務量となった。これを指揮したのが、当時の大学院部長、藤田若雄教授(労働運動史)であり、池内和子(室長)、岩田みよ(和文タイプ・印刷)、福升俊夫(文部省関係)という強力なスタッフがこれを支えた。本館 2 階北側の事務室は毎晩遅くまで準備に追われ、申請の前夜には徹夜の作業となった。並木は事務室に出入りして教員との連絡と文書作成に従事した。大学院事務室のチームワークと連日連夜の奮闘は見事であったと言うほかない。このことを特に記して30年遅れの謝意を表したい。 III 比較文化研究科の発展1 比較文化研究科は幸いにして文部省の審査を通過し、1976年4月に博士前期課程の開設、5月の入学式、クラスの開始、そして2年後の1978年3月の卒業式で修了生を送り出して、前期課程を完成した。その翌月、1978年4月に博士後期課程を開設した(4名入学)。以来、前期、後期課程の新入生を順調に迎えて、後期課程の開設から10年後の1988年には、最初の課程博士授与が行われ、3名(稲田敦子、森洋子、棟居洋)の諸氏が学術博士を認められた。現在までの修了生の数についてはすでに述べた。前期課程の第一回修了生のうち、中村一郎、守屋靖代の両氏は現在本学の有力な教員である。 2 比較文化研究科には、開設当初から社会人類学分野、コミュニケーション分野の専任教員を確保する課題があった。社会人類学については、曲折を得て次第に充実した。青柳清孝(兼担)、宮永國子(専任)両教授を得たことは、大きな意味があった。その他、音楽学、フランス史、中国史、朝鮮史などの分野も専任者が得られて、授業科目が豊かになった。魚住昌良教授(ドイツ史)の着任は開設時であったと記憶する。研究科の分野が豊かになる方向性にあることは心強いが、弱体化した分野もある。現在は社会人類系の専任教員が再び欠在であり、その充実が望まれる。 3 開設以後、比較文化研究科は学外から著名な教授たちを迎えた。開設時には、峯村文人(日本文学)教授が着任し、その後、源了圓(日本思想史)、福田秀一(日本文学)、小泉仰(日本思想史)、斯波義信(中国史)、飛田良文(日本語学)の諸教授が着任し、学問分野の視野の拡大、博士論文指導の充実に多大な寄与をされたが、それぞれこの間に大学院教授の定年を迎えて現在では惜しくも退任されている。村上陽一郎(科学史)は東京大学での定年を一年残しての着任であり、その後「オスマー記念教授」の誉を受けておられる。 4 比較文化研究科は開設時よりも学問分野を広げてきたが、「日本言語文化教育研究プログラム」は研究科拡充の歴史の中でも最大のものであった。 ICUは教養学部の開設した1953年に早くも留学生のための日本語教育プログラムを開始しており、この国の大学における日本語教育システム構築のパイオニアであった。比較文化研究科は日本文化研究における日本言語文化の不可欠なことを認識していたが、語学科の日本語教員全体との関わりを構築できないままでスタートした。開設時に語学科よりのN. Brannen教授(日本言語学、翻訳論)の着任を得たことが、語学科との唯一のつながりであった。 教授会に籍を置く日本語学教員全体の比較文化研究科への所属と新規プログラムが検討されたのは、Brannen教授が退職後のことである。英語学関係教員は早くから教育学研究科の教育方法学専攻において英語教育法のプログラムを担当していたが、日本語教育の教員は所属する研究科を得ていなかった。日本語教育に関する大学院を設立する動きが全国的に活発となった1980年代後半に入って、本学でも日本語教育に関わる大学院の必要性がますます感じられるようになった。関係教員の熱意が執行部を動かして、1986年に源了圓教授を委員長として、本学の教育研究プログラムの充実を図る方向で、大学院レベルの日本語教育プログラムと所属すべき研究科とを検討する委員会が発足した。所属すべき研究科については、曲折を経て比較文化研究科に決まり、「日本言語文化」を博士後期課程までを持つ第二の専攻として新設し、日本語教師を養成できる人材を育成することを主たる目的とすることが合意された。 この合意により、1989年に福田秀一教授を委員長する設置準備委員会が発足した。しかし内外の日本語教育著名教授を招聘する試みは当時の需要供給のバランスの問題もあって大方挫折し、着任を得たのは飛田良文教授のみであった。またこの間に学内の人材が流失し、財政状況の変化などもあったため、比較文化研究科内に第二の専攻を設立することを断念し、比較文化専攻内の一つのプログラムに収めることにした(1994年)。その結果が「基礎科目群C」などの新設として、現在の授業科目構成に反映されている。このような経緯を経て日本語関係教員の所属が実現したのは1995年であった。なお、その後比較文化研究科には、語学科のフランス語関係教員も所属して現在に至っている。 この日本言語文化の学科目と教員の充実は比較文化研究科の内容を豊かにした。とくに留学生たちには大きな魅力となり、今日まで着実に優れた修了生を送り出してきた。 IV ICU 比較文化研究会の発足と発展比較文化研究科の大きな特色は、「ICU比較文化研究会」の活動である。研究科が博士前期課程の学生数を着実に増やし、後期課程の学生が一定数に達して学問的な発言の実力を獲得した開設から4年目に、この研究会は研究発表と相互批判の場を確保し、研究成果を内外に公表することを主たる目的として発足し、現在に至っている。本学の他の研究科には見られない研究団体である。その特色を箇条書きに記しておきたい。 1 この研究会は、学生と教員が共同して組織する学内学会である。 研究科長が研究会の会長となり、学生(修了生を含む)が運営の実行に当たる(運営委員長、その他の委員)。設立総会は1980年5月20日。発足当時の会員数39名(賛助会員を含む)。 2 研究紀要『ICU 比較文化』を刊行して現在に至る。 研究会は編集委員会(編集委員長は教員、他の委員は学生)を置き、掲載論文の決定(レフリーに委託)、編集、印刷所に送付、執筆者への校正依頼などの努力をする。紀要は1993年までは大体、年2回の刊行、1994年以後は年に1回の刊行で、現在までに38冊を刊行した。また会員への配布のほか、主要研究機関に寄贈している。 3 研究会は教員と学生相互間の意見交換の機会を設ける。 これまで、紀要刊行後に合評会を行い、相互に批判し、意見を交換してきた。夏期合宿においては親睦の傍ら、口頭発表と議論を行ってきた。修士論文提出、審査会終了後に、執筆者による修論報告会を行う。最近では指導教員がまず批評し、参加者による討論が行われている。 4 研究会は研究環境の維持に責任を持つ。 PCの管理、コピー機(レンタル)管理、個人が使用する研究机の割り当て、セミナー室使用の規律などを定め、問題が発生した時には大学側との交渉の窓口になる。 5 研究会は適宜、博士論文を刊行する。 a 一般書店からの学術論文刊行の困難を考えて、執筆者による出版費用を軽減しつつ著書刊行の実績を作る。 b 国際基督教大学大学院における研究業績を公開する(主要大学の図書館への寄贈)。 c 学位論文の叢書の出版を通して、ICU比較文化研究科の研究者養成能力を世に問う。 d 組み版作業の内製化などにより、出版費用を抑さえて、若手研究者にも購入しやすくする(比較文化研究会の会員には割引で販売する)。 e 学外に ICUの研究者養成能力を証示して、本学の広報に役立てる。 およそ以上のような了解のもとで、研究会内に博論出版委員会が組織され、フォーマットの確定などの努力を積み重ねて、1992年3月に叢書の第1冊を刊行、2006年4月に第6冊を刊行した。(書名は後述VI-Eに掲げる。) V 比較文化研究の大学院を保持する意味1 「比較文化」だけを名称とした研究科の設立は日本では初めての試みであった。ちなみに東京大学では「比較文化・比較文学」を研究科の名称としていた。初めての試みであるだけに、1975年に文部省に提出した設置申請書の冒頭に記される「目的」の叙述は簡潔であっても、要を得たものでなければならない。ます、設置の心構えを (a) 国際的に異質な文化を比較研究、(b) 各種の文化の相違点と同一性の解明 、(c) 国際理解の推進への貢献、の 3 点において示し、この研究科の研究方法の特色を (a) 広義の文化を研究対象とするので学際性を持つこと、(b) 現代は文化・社会の変動の時代ゆえに、「問題指向的」(problem oriented)方法を採用すること、(c) 現行の各種の専門分野(discipline)の学問を学際的な比較文化との関連で新しく探索することの 3 点にまとめている。 2 この叙述の背景にあったのは、準備段階で大塚久雄教授が関係者に示した「覚書」(1973年)であった。それは以下の5点にまとめられる。 a 比較文化の研究姿勢はproblem oriented であること。それは抽象的な法則認識を指向する専門分科(discipline)ではなく、「医学」に見るよう な問題解決的な学問把握の達成を目指す。 b 現今の問題は異文化間の相互理解の達成である。 c 研究対象を限定する必要がある。たとえば、東アジアと西ヨーロッパ(アメリカ)文化との比較。宗教(とくにキリスト教)と諸文化との関 連。どのような比較研究においても、歴史的な観点(究極的には世界史的な観点)を忘れない。 d 「文化」の定義は最広義とする。「人類が作り出し、かつその中で、またそれによって生活をつづけてきたようなすべてのもの」のように理解し ておく。それにより、「宗教・思想・価値観・学問・芸術そして政治・社会経済等々の諸領域がすべて包摂される」。 e 「比較」とは、「相似」と「差異」の認識から出発し、異文化間の相互理解を可能にする方法を学問的に追究する。「比較」は特定の文化それ自 体の研究を排除しない。むしろそれは比較のための不可欠の前提であると認識する。 3 この路線に沿って比較文化研究科設置責任を引き受け、初代の研究科長を勤めたのが山本達郎教授であった。山本教授は編著『比較文化の試み』研究社、1977年の始めに置かれた長い序文「比較文化のすすめ」(iii-xviii頁)において、「比較文化」の必然性と課題、この学問の方法を記した。それを箇条書き的にまとめておこう。 a 平和維持の基本となる国際理解推進のための組織的研究は未発達である。 b 国際理解の学科目を担当できる教師を育成する必要がある。 c 西洋文化の絶対的な優位喪失は複数文化の比較研究を促進するはずである。 d 各文化に平等の「市民権」を与えて研究する。 e 科学技術の進歩とは別の角度から異質な文化を探求する。 f 一民族・国家の理解のためにも、他民族・国家との比較が必要である。 g 外国人による日本研究が日本人の研究より成果を生む可能性がある。「日本文化の微妙な味わいは日本人でなければ分からない」という思い込み は、文化の「特殊性」をも掴み得ない。科学的認識には比較が不可欠である。 h 人間性・人類性と呼ばれる普遍性の実体を経験的に把握する必要がある。 i 文化の連続性の中での比較研究(例、日韓、仏独の比較)と文化の連続性を超えた事象の比較(例、ローマと中国の婚姻法の比較)との相違を認識する。 j 「文化研究」は内からの理解(人文研究)と外からの観察を併用すること。これは思想史の方法に典型的に見られる。 k 比較作業のための「参照枠」(frame of reference)を理念型的に構成する必要がある。 l 比較を成立させるためには「世界観・人間観」が不可欠であり、経験界、歴史的な世界を乗り越えた洞察や先見が意味を持つ。そこに宗教の役割 がある。比較文化研究科が歴史と宗教に重点を置くのは理由がある。 4 教員側のこのような意気込みと構想の下で比較文化研究科はスタートした。しかし、比較文化の研究方法を教員が常に自覚的に実践したわけではない。有力教授たちを除けば、大多数の教員たちは比較文化の方法を自分でどのように構築すべきかにとまどいを覚え、基礎論としての個別の研究に向かわざるを得なかった。比較文化研究科開設から4年後に「比較文化研究会」が発足したが、その設立総会日(1980年5月20日)に持たれた第1回研究会においては、その点に対する学生たちの批判的なが意見が提示された。その日、シンポジウムとグループ討論が行われ、『ICU比較文化』創刊号に議論が要約、収録されている。文末には(Su)の署名がある(当時の学生側のリーダーであり、現在は群馬大学で教えている砂川裕一氏の筆であろう)。 この時の議論は今読んでも興味深い。シンポジウムでの自己批判的意見として、「比較文化という概念の無規定性、それに起因する研究科それ自体の方向性の欠如」、「比較を棚上げにした比較文化」、「単なる個別の寄せ集め」などの言葉が拾える。グループ討論では、次のような意見が出されたという。 歴史・思想史グループでは、比較文化と言っても、実際には史料によるケース・スタディーにならざるを得ない」との発言があり、宗教グループでは「人生の究極的意味、whyを問う」との姿勢の表明があり、文学グループでは「比較文化以前に、そもそも文学とは何かが問題だ」と指摘された。当時の学生たちのとまどいを如実に反映している。 Su氏は、この日の議論を反省して、比較文化の学問的独自性に関する二つの思考軸を提示した。 a 「比較」は方法的態度、個別研究で自ずから要請されてくる。 b 「比較文化」は諸領域に対し、その関係性に留意するが、メタの立場に立つ。 さらに、学問の「対象」と「主体」との関わりについて、この日に見られた二つの姿勢を指摘した。 a 対象と主体との短絡を避けて、学問の客観性を保持する。 b 主体と対象の相互規定的・主客未分の層において対象を把握する。 「比較文化」の研究に不可避な困難がつきまとうことの鋭い認識が表明されている。遅ればせながらの敬意を表したい。 VI 比較文化研究科を実践した成果-評価と課題第一に注目すべきは、比較文化研究科を修了した学生たちの数である。大学院の成果は博士前期課程においては「文学修士」号の授与数、博士後期課程においては「学術博士」、後に「博士(学術)」の授与数で端的に示される。講演の始めに現状認識としてすでに紹介したように、2006年3月時点での学位受領者は前期課程が332名、後期課程の課程博士が45名、論文博士が11名である(内、5名が後期課程出身者)。 A 比較文化研究科在籍者についての観察 1 学内の他の研究科においても同じ傾向があると思われるが、比較文化研究科においては、教員側、学生側ともに、リベラル・アーツの延長上に 研究科が存在しているとの意識が強いように見受けられる。 2 比較文化研究科は伝統的に内部進学率が高い。 3 特に後期課程への進学者の比率が他研究科よりも高い。 4 博士前期課程では男子学生に対する女子学生の比率が4研究科中で最も高い。 5 経験的に見て、比較文化研究科では博士後期課程に関係する学生(在籍者、休学者、一時退学者)の数が多く、活動力が確保されている。 B 博士学位取得状況 1 1997年度(開設から18年目)までの課程博士学位の取得者は18名であった。ちなみに歴史の古い教育学研究科は19名、行政学研究科は16名であった。比較文化研究科においては、在籍者に対する博士学位の授与率は22.2%であり、3研究科の平均は20.2%であった。比較文化研究科が課程博士の学位の取得意欲のある学生に恵まれていることを意味する(ちなみに2005年度の人文科学系の課程博士学位取得の全国平均は7.1%)。 2 このことは、表に示されている2006年度までの比較文化研究科における課程博士学位の取得者45名が3研究科中で最多であることからも明らかである。ちなみに教育学研究科は36名、行政学研究科は39名である。課程博士学位の授与を大学院教育の完成と考えれば、比較文化研究科は博士課程の設置が遅れたにもかかわらず、3研究科中で設置の目標をもっとも達成している。 C 課程修了者の進路 1 1992年度『就職のしおり』の図表からの推定であるが、比較文化研究科の博士前期課程修了者の就職分野は学部学生とほぼ同じである。しかし前期課程から後期課程への進学者の比率は推定で4割であり、他の研究科の2倍を超えると思われる。比較文化研究科の学生たちは研究の続行への意欲が高い。 前期課程を修了して国内他大学の後期課程に進学した者、その後は独学によって大学教員職を得た者も見受けられる。 2 博士課程在籍者の進路は研究職への就職が目立つ。博士学位取得者の研究職への就職率は高い。 また、他の職業分野に「転身」して視野の広さの強みを発揮している者がいる。芥川賞受賞作家の奥泉光氏、東北弁使用のシェイクスピア劇団の主宰者の下館和巳氏はともに大学教員を兼職している。 大学院出身者に対する進路調査は、本学における大学院保持の意義を確認し、学生たちの入学・研究意欲を強めるためにも重要であり、実施が待たれる。大学院での経験の活かし方は多様であろう。卒業生たちのシンポジウムが開かれれば、興味深い話が聞かれるように思う。 D 博士学位論文「ICU 比較文化叢書」の出版 これまでに「比較文化研究会」が刊行した学位論文(正確には、提出した学位論文に手を加えた著書)は以下の6点である。 1 棟居洋『ドイツ都市宗教改革の比較史的考察-リューベックとハンブルクを中心に』1992年3月 2 上尾信也『楽師論序説-中世後期のヨーロッパにおける職業音楽家の社会的な地位』1995年4月 3 山森みか『古代イスラエルにおけるレビ人像』1996年4月 4 高崎恵『自己像の選択-五島カクレキリシタンの集団改宗』1999年4月 5 安田夕希子『穢れ考-日本における穢れの思想とその展開』2000年4月 6 五郎丸仁美『遊戯の誕生-カント、シラー美学から初期ニーチェへ』2004年4月 E 博士学位論文の一般書店からの刊行 1 安達かおり『イスラム・スペインとモサラベ』彩流社、1977年 2 横山泰子『江戸東京の怪談文化成立と変遷』風間書房、1977年(日本古典文学会賞、歌舞伎学会賞) 3 谷村玲子『井伊直弼 修養としての茶の湯』創文社、2001年(日本茶道学会賞) 4 平田松吾『エウリピデス 悲劇の民衆像』岩波書店、2002年 F 大学院在籍者の出版活動の若干例 1 高橋弘『素顔のモルモン教』新教出版社、1996年 2 大西直樹『ニューイングランドの宗教と社会』彩流社、1977年 3 斉藤栄一『往還する視線』近代文芸社、2001年 4 宮武久佳『知的財産と創造性』みすず書房、2007年 以上は出身者による出版活動の若干例に過ぎない。大西直樹氏には他の著書があり、横山泰子氏、上尾信也氏などの活発な著作活動を展開している。高崎恵氏によるマリンズ『メイド・イン・ジャパンのキリスト教』翻訳などは学術的な仕事である。 G <総括的評価> 以下は私の経験に基づく判断である。 a 大学院出身者の多くが社会において「比較文化」を意識して培った総合的な知を活かしている。 b 教育・研究職に就いた者は広い知見を活かし、比較文化の精神を学生たちに広めている。 c 国外で日本語・日本文化の伝授を比較文化的な視点から実践している者がいる(テルアビブ大学の山森みか氏など)。 H 比較文化研究科の存在意味と形成力 ICUにおける「比較文化」の位置についての私見を記しておこう。 a 比較文化の学問性はICUのリベラル・アーツの精神と設立時に目指した高度の専門教育(大学院大学)の理想との結合として理解される。 b 比較文化研究科はリベラル・アーツの完成であり、エリート教育の使命を達成している。エリートとは、高度の専門知識、広い視野、知的総合 力、深い人間観・世界観、人類に対する使命感、先見性の持ち主である。 c 「リベラル・アーツとは何か」という問いは既存の解答を持たず、実践を通して各自がその意味を追求する。リベラル・アーツをより高度のな 専門研究の予備的な訓練と見なすことは誤りである。リベラル・アーツと専門研究はフィードバックの関係にある。「比較文化」はとくにその 傾向が顕著である。それは授業科目のほとんどを高学年の学部学生が受講できるように始めから計画し、開講してきた研究科の姿勢において明 らかである。 d 「比較文化」の研究方法は、教員と学生の双方において、各自が教育研究の実践を通して開拓すべき課題であり、社会と時代の変動とともに課 題も変化する。開設時における研究方法についての留意は卓見であった。比較文化は、抽象的な理論構築から出発する「演繹」的方法を避けなけ ればならない。「比較文化」の意味は、学際的な視野を持つ個々の研究とその総合を通して、徐々に納得されるであろう。比較文化の「無規定 性」はこの意味で戦略的に貫かれる必要があろう。「問題指向的」な視点は仮説的な研究と思考実験の繰り返しを要求する。それは比較文化に 固有な方法ではないが、比較文化研究科がこの方法をもっとも自覚している点に研究科の存在意義があろう。 e 「比較文化」の学問性を追求し、これを築く原動力は、まず学生たちの意欲と能力である。「比較文化研究会」のこれまでの活動がそれを証し している。 f 比較文化研究科の教員たちは、自らの講義、演習を通して、学生たち以上に「比較文化とは何か」の問いに直面する。その緊張感の持続が比較 文化の学問の方法を開拓する条件である。推測ではあるが、この研究科の教員は、修士論文・博士論文審査会、博士候補資格取得のための論文 審査会において、他の審査委員の質問もしくはコメントに反応して、教員間で意見を交換することが多い。それは教員たちにとって、学問対象 に対する新しい方法と視角を得て、問題意識を深めることができる貴重な機会である。 この事実は、比較文化の学問性と研究指導に積極的にコミットできる教員とそうでない教員との実力の開きが増大することを意味する。この研究科の質の保持のためには、教員の自己検証が極めて大事である。 VII 「比較文化」研究を推進するための若干のコメント以下の諸点を思いつくままに記しておきたい。 1 「問題指向的な」研究の困難の自覚 設立当初の問題指向的な学問形成の指針は正しかった。設立時代における異文化間の相互理解の課題は、現代、ほとんど対立状況に置かれた文明を相互に理解できるのかという深刻な問題を提起している。思想界は「異質な他者」に差し向かうための基礎的な理論作りに苦労している。人間観・世界観の役割、対象に関わる自己の主体のあり方が問われる。「比較文化」がそれに答えるのは極めてむずかしいが、放棄できない課題である。 2 「比較」のための諸種の準拠枠を理念型的に提示する努力 この講演の準備において、私は比較文化研究科設立の責任者であった山本達郎教授の先見性を再確認した。経験的な事実を整理して比較を可能にするための諸種の「準拠枠」の制作が確かに必要である。「比較文化」の「文化」の理解を最広義に設定したのは、大塚久雄教授の寄与であった。それによって研究対象の固定化を免れ、専門分野も関心もさまざまな教員たちが研究科に参加できた。学生も自由に関心を設定できた。 文化を広義に定義することは、研究対象と研究体制の確保に必要である。しかし、それは文化概念について反省しなくてよいということを意味しない。むしろ、文化の比較を分析的に行うためには、「文化的な」と言われうる事象を人間の政治社会の成熟の達成との関わりで、厳密に考えておく必要がある。「文化」と「文明」との関わり方を考察する基盤も問われる。文明に対する文化の批判的役割の有無、その程度と態様も問われる。差し当たって文化と文明という二つのアスペクトを対照的に捉える判断の準拠枠をそれぞれが作っておく必要があろう。それはメタの視点として作用するはずである。これは比較文化研究会での共同研究と してもよい。 3 「文化」の二つのアスペクトを考える 本学で源了圓教授が主導した共同研究の一つが、「型の文化」の研究であった。共同研究は『型と日本文化』(創文社、1992年)として公刊された。「型の文化」が文化の中の特殊な日本的なものという理解があるとすれば、それは適切ではない。私見によれば、「型の文化」と対置される「かたちの文化」という類型を提示することができる。両者のアスペクトが入り混ざりつつ、しかしどちらかが優勢であるのが、諸文化の実態であろう。 「型の文化」においては、シニフィアンとシニフィエの対応そのものに注意が払われる。その意味では、それは「象徴」の文化であるとも言い換えられる。(コードを重視する文化であるとも言える。)それに対して、「かたちの文化」はシニフィアンとシニフィエの間を一回的に架橋する個々人の思考、ときにはパーフォーマンスに意味があり、その架橋に人々が参加する。(テクストの読解もまたパーフォーマンスの一つである。)西洋における「再現芸術」が有効な文化活動となる。オーディエンスが演奏家の架橋に参加し、賛同または批評する。それは市民社会が「公」と「私」を架橋する「公共性」の創造(それは起源的には個々の自由人と都市団体の間に超越的に存する「法」の創造に対応)と構造的に重なっている。そこから政治思想史的な考察へと道が開かれるであろう。二つの文化の重層構造のあり方が諸地域の文化では違う。 文化の二つのアスペクトの研究、その準拠枠の仮説的な構築は政治、宗教、文学、芸術、社会の総合的な見方と個々の主題における分節の仕方を教えるものではないかと思う。文学の領域では、二つの文化は「物語」と「小説」の対比に展開できよう。「物語」の基盤には共同体志向が存在する。これは再び政治団体との対比に持ち込まれるであろう。 このようなテーマも共同の検討に値すると考えたい。(講演時においては「文化」と「文明」など、幾つかの事柄を二項対立的にまとめた私見を参考までに配布したが、ここではその提示を省く。) 4 「言語」と「文化」の問題 たとえば「日本言語文化」という一つの成句が通用する。確かに言語と文化は不可分ではあるが、区別も必要であろう。異文化の言語は他文化にそのまま置き換えられない。そのズレが文化内容の伝達をときには制限し、ときには豊かにした。「翻訳」の問題が典型である。東北学院大学の下館和巳教授のようにマクベスを東北の時空と言語に移して、作品を丸ごと「翻案」すると、原作とも、自由な書き下ろし作品とも違った第三の次元の、解釈の射程範囲の広い作品の創造となる。 「翻案」は「パロディー」と構造的な関係がある。パロディーは換骨奪胎の言語技術である。パロディーに関しては、最近の一クラス(担当者クリステヴァ教授)で文学と芸術関係の教員たち数名が参加し、それぞれの領域での実例を取り上げたと聞く。このような試みが共同の課題として、より公の場で組織的に行われてよいだろう。 5 科学史、STSの領域を活かすプログラム 現在の比較文化研究科の科目では対応が不十分である。この領域がリベラル・アーツにおいて重要であることはつとに認められている。大学院レベルにおけるこの領域の充実は「問題指向的」な研究への大きな刺激を与えるであろう。(この事柄は村上陽一郎教授に十分論じていただきたい事柄である。私は事柄だけの言及にとどめたい。) VIII 講演を終えてこの講演は、比較文化研究科開設30周年記念行事の運営委員会から急の依頼を受けて短時間で準備したので、大学院事務室の助力を得たが、十分な調査を行ってはいない。しかし、比較文化研究科の30年の歩みのおおよそのところは紹介できたと感じている。私は準備作業の一つとして学生たちの修士論文、博士論文の題目に目を通し、その多様さに驚いた。私は比較文化研究科が学生たちにとって、まず問題発見的な大学院としての意味を持ってきたこと、また学生たちが早くも修士論文においてそれぞれ自立的な研究を行っていることを認識した。 比較文化研究科の卒業生たちはそれぞれの分野で知的個性を発揮し、厳しい競争を経て大学その他の研究機関で職を得ている。この知識社会への適応力は、卒業生たちがこの大学院の在籍中に獲得した知的柔軟性によるところが大きいであろう。 私は講演後、校務で出席できなかった一人、法政大学で教えている横山泰子氏にレジュメを郵送したところ、早速返信が着き研究者仲間の中での自己の学問的な姿勢の独自性に筆が及んでいた。横山氏によれば、既成の民俗学、美術史の枠内で研究している仲間たちはそれぞれ閉鎖的な学会の中で研究対象と方法についての枠を破る難しさを嘆いているが、自分は何を書いても研究者たちから越権行為と言われることがなく、これまで自由を満喫できた。これは着想を自由に展開できた比較文化研究科に在籍できたからではないかと考えると、振り返って「まことにありがたい場所であった」との思いを持つとの趣旨の感想をいただいた。おそらく他の出身者も同じように感じているのではないだろうか。 大学院生が広い学問的な視野を持ち、自立的な研究能力、発表能力を養うためには、それぞれに違う分野の研究関心を持つ者たちが、自己の研究意図と意味とを説得的に伝達する「対話」の試みを積み重ねる必要がある。そのためには専門的な分野の大きな大学院が有利であるとは言えない。大きな大学院では、大学院生が異質な研究分野の研究を志す学問的な他者たちに取り囲まれることはなく、自己の学問関心の説得と無理解な批判に受け答えする対話の必要が減ずる。しかし、対話をくぐることなしには自己の学問は他者の心には届かない。この対話の重視と維持こそは、比較文化研究科の大きな特色であり、「比較文化研究会」が活動する意味である。研究会は在籍学生たちによって担われる。ことに後期課程の学生たちの積極的な参加は、研究者としての自立の仕方を前期課程の学生たちに示す意味で重要である。研究会の意味を自覚して自発的に活動にコミットする学生たちが、今後も絶えず研究会において確保されることを望みたい。 「継続は力なり」と言う。研究紀要『ICU比較文化』の刊行、学位論文の刊行は比較文化研究科の実りを端的に世に問う貴重な仕事である。学位論文の刊行には博士後期課程の学生たちの意欲と自発的な奉仕が欠かせない。出版活動今後も継続されるように期待する。 目下、学内の大学院の統合に向けた改革案が検討されているとのことであり、このことについて講演後に質問を受けた。統合について私は軽々に意見を述べるべきではないと考えたが、「比較文化研究科の特色をよりよく発揮できるような、ある程度の統合は可能であろう」、「いかなるかたちを取ろうとも、比較文化研究会を持続する必要があろう」と述べた。この問題を決着させる責任を負う教員各自が比較文化研究科開設30周年を迎えた今、研究科の特色と課題について、またこれまでの実りについて顧み、認識を深めて、大学変革に時代に適切な対応がな されるよう、心から期待する。(2007.2.6) |
|