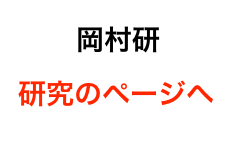Education


Contents
教育についての提言: 文理両道のすすめ
1.文系学生を対象とした物理教育
科学を知らなくても「何も困らない」のに,なぜ科学を勉強するべきなのか.「教養としての」物理とは何か?
Albert Einsteinは、“Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.” という言葉を残した。文系学生に例え物理学の公式を教え込んだとしても、ほとんどの学生は1年もたたずにその内容をすべて忘れてしまうだろう。また、インターネットが普及した今の時代、検索すればすぐに分かるような知識を学生に教えこんでも、それは教育として何の価値も持たない。教えるべきは科学という視点であり、その精神及び考え方である。
しかし文系学生はそれまで一切、科学の考え方に触れてきていない。人は一般に、自分と違う考え方を受け付けることはできず、反発してしまう。反発されてしまっては教えることが不可能になる。そのためこの授業では、科学を異文化として紹介する手法をとっている。アメリカ人が土足で家にあがってきたとして、アメリカの文化を知らなければ非常識だと怒るだろう。しかしその文化を知っていれば、理解することができる。異文化コミュニケーションという枠組みで科学を捉えれば、反発を招かずに科学の考え方を教えることができる。
CPスノウの「2つの文化」になぞらえ、日本版の「2つの文化」を説明する。2つの文化、H-culture、S-cultureはどのように違った文化なのか? 論理の違い、「真実」の取り扱いの違い、言葉の意味の違い、エビデンスの扱いの違い、目的設定の違い、議論の仕方の違いなどを説明する。
S-cultureを、理系学生は長い時間をかけて体験として習得して行く。しかし文系学生は大学でたかだか1つ程の自然科学系列の科目しか履修しない。そのたった一つの機会に科学のエッセンスを凝縮して教える方法はないかと、考えたのは、自由研究である。
一般教育(GE)内での自由研究の進め方 (Japanese) (English)
2.理系学生を対象とした科学教育
ディスカッションを通じて4年間の学びの統合をするICU伝統の「総合演習」
大学院講義「科学教育論」
3.物理専攻生を対象とした物理教育
主な講義 Lectures
現代物理学 I (光学から量子論まで)
レーザー物理学(大学院講義)
実験 Lab courses (テーマ選択制)Details
基礎物理学実験 I (力学、波動、屋外実験)
物理学実験 I (ホログラム、他)
現代物理学実験(レーザー発振、位相共役波など)
少人数制を活かしたコース
アドバンストセミナー(少人数制)(internal site)
4.子供を対象とした物理教育
子どもは実験が好きで、素直に面白がってくれるが、ただの遊びにならないように、そこに汎用的な物理が隠れていて、さまざまな現象や機械に同じ原理が活かされていることを分かってもらえるように留意している。
文部科学省サイエンスパートナーシッププログラム(SPP)のページへ
5.大人を対象とした科学の啓蒙活動
大学生以上に対しては、子供の場合と違って、理科の面白さを伝えることは目的ではない。理系的視点を使うことで、どのように判断が異なってくるのかに気づいてもらい、科学的手法の重要性を理解してもらうことを主目的とする。Critical thinkingの導入として必要不可欠。
Critical Thinkingのページへ(under construction)